“最強の柔軟性”を持つサッカーのフォーメーション
サッカーにおけるフォーメーションは、チーム全体の戦い方を大きく左右する重要な要素です。4-4-2や4-3-3、あるいは5バックなど、チームの個性や選手の特性に合わせて無数のバリエーションが存在します。
そんな数あるフォーメーションの中で3-4-3はおもしろいシステムだと考えています。一見すると守備重視の3バックかと思いきや、実は“選手の特性”や“試合の状況”に応じて形を大きく変化させることができる「究極の柔軟性」を備えたシステムとして、多くの監督が採用を検討しています。
イタリアをはじめとするヨーロッパのクラブでも、3-4-3の応用例は増えてきました。特に2016-17シーズン、チェルシーを率いたイタリア人監督のアントニオ・コンテがこの3-4-3を成功させ、プレミアリーグ制覇に導いたことは有名です。ワイドに配置されたウイングの選手がハーフスペースをうまく使い、相手守備に混乱を与えたあのスタイルは今でも語り草となっています。
では、なぜ3-4-3は“究極の柔軟性”を持つといわれるのでしょうか? その秘密はどのような仕組みで成り立っているのでしょうか? 本記事では、3-4-3が生まれた背景や基本的な配置のポイント、そして攻守における具体的な強みと応用例を紐解いていきます。
イタリアから生まれた“3バック革命”と3-4-3の歴史
イタリア発祥の“3バック文化”
現代サッカーの3バック(3人のセンターバック)戦術と聞くと、まずイタリアを思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。もともとイタリアでは、3-5-2が伝統的な布陣の一つとして確立されていました。
これは「堅固な守備をベースに、中盤の枚数を多くしてバランスを保つ」という意図のもと、イタリア特有のカテナチオ文化とも相まって発展してきたものです。
ここで攻撃面を強化するために単純に3-5-2の“一人を前線に上げる”アレンジも試みられてきました。そこで生まれたのが3-4-3です。つまり、本来中盤にいた一人を最前線へ押し上げることで、より攻撃的な姿勢を示しつつ、3バックならではの守備安定感を残そうとしたのです。
“3-4-3”の象徴的成功例:コンテのチェルシー
一方で、同じ3-4-3でも配置や動かし方は監督によって大きく異なります。たとえば1990年代のイタリアサッカーでは、ミランなどのクラブが変形3バックを敷きつつ、中盤の底に“レジスタ”を据える形が見られました。しかし、時代を経てより多彩なアレンジが登場する中で、大きな注目を集めたのがアントニオ・コンテのチェルシーです。
2015-16シーズンに低迷したチェルシーへとやってきたコンテは、翌16-17シーズン開幕当初こそ4バックを試行錯誤していましたが、途中から3-4-3へ切り替え。すると、ウイングバックのビルドアップ参加とフォワードの“スペース”活用が一気に機能し、チームは怒涛の連勝を重ねて優勝まで駆け上がりました。
このとき注目を集めたのが、ワイドに開きすぎず、それでもサイドラインを有効活用する”ウイングの配置です。相手のDF陣を全員同時に困らせる絶妙なポジショニングが、チェルシーを“無敵”に近いチームへと変貌させたのです。
3-4-3の柔軟性を生み出す具体的ポイント
ここからは、3-4-3がどのように“形を変えながら”試合を進めていくのか、具体的なポイントを見ていきましょう。
ビルドアップ:3バックの多様な役割分担
3バックでは、まずセンターバック(CB)が横一線に並ぶ形が基本です。しかし、試合展開や相手のプレス方法によっては、**1人がボールを持って前進(ドリブル)し、他の2人がワイドに広がってパスコースを確保するなど、自由度が高いのが強みです。
特に相手が前線に3人を配置して3バックに対してプレスをかけてくる場合には、“可変4バック”に変化することもあります。具体的には、
- ウイングバックの一人が後方に下りてきて4枚を作る
- キーパーを1枚のフィールドプレーヤー的に活用して、本来ISB(インサイドバック:3バックの際の両サイドのバックを指す「メソラボのオリジナルです」)をよりワイドに広げる
- ボランチが1人CBの間に落ちてきて数的優位を作る
このように3→4人の後方ラインへスムーズにシフトすることで、相手のプレスをかわす手段が格段に増えるのです。
ワイドの活用:ウイングバックとWGの連携
これより先を読むには【有料会員登録】を済ませてください。
*このページ区間はすべての会員様に常に表示されます*

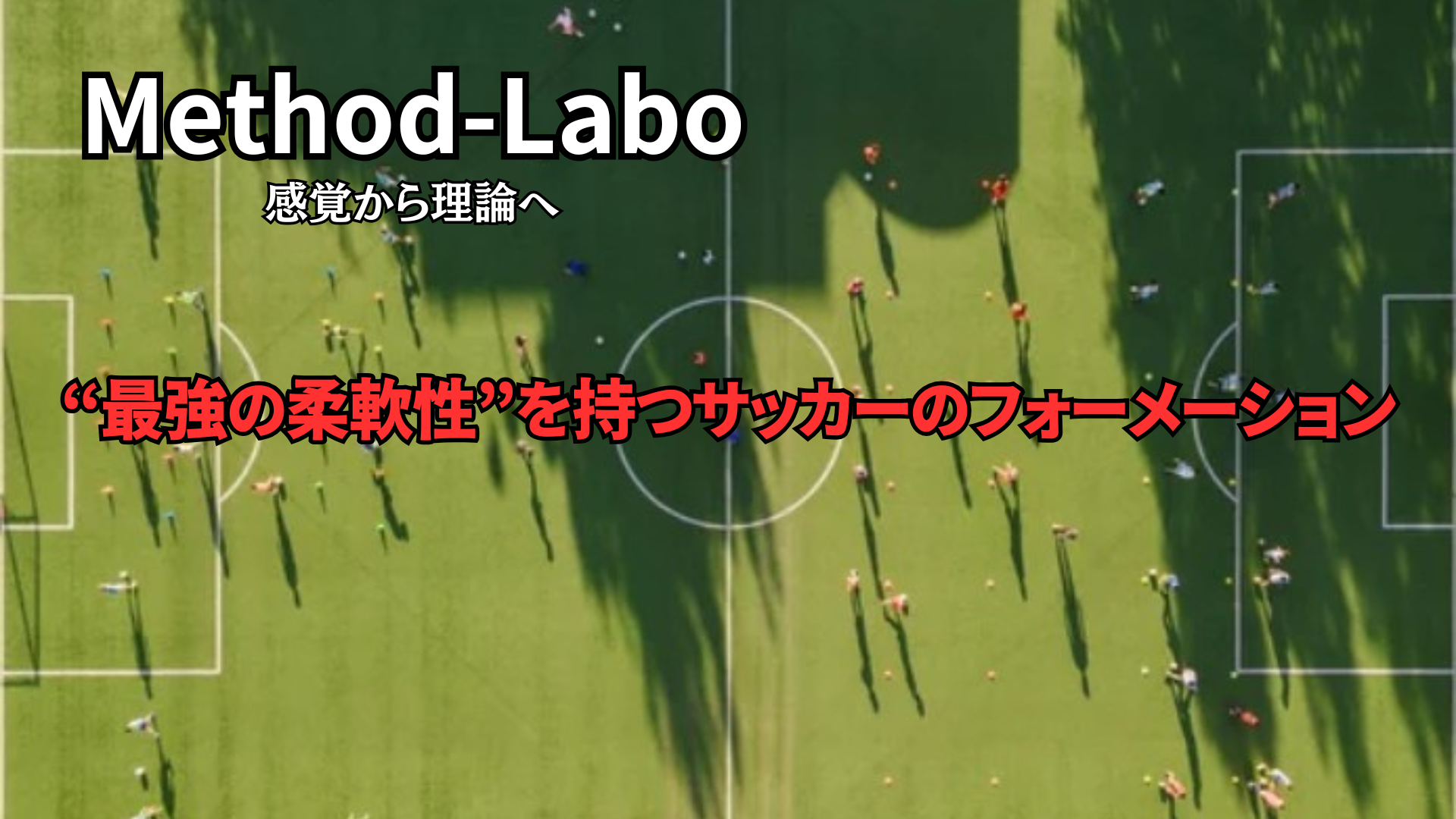
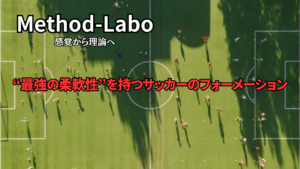
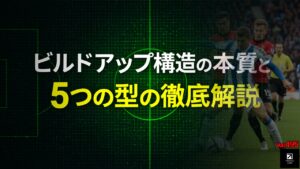







コメント