はじめに
ふと気になったのでまとめてみました。
サッカー選手の寿命とその後です。
華やかな舞台で脚光を浴びながらプレーしているように見えるプロの世界ですが、実際には「プロとして在籍できる期間が短い」「出場機会を得られるかどうかは熾烈な競争に勝った者のみ」など、厳しい現実を伴う世界でもあります。
ひとたびプロ契約を勝ち取っても、数年で現役の舞台から去る選手がいる一方、長く第一線で活躍し続けるベテラン選手も存在します。ここで疑問なのが「現役生活はどのくらい続くのか」「総合的に何分ぐらいの出場時間を得られるのか」が気になるところです。
さらに、引退後にどのような仕事に就き、どれくらいの収入を得て暮らしているのかもサッカーファンならずとも興味のある話題ではないでしょうか。
プロになるということはプロでなくなる時が来ます。夢を追いかけるのはとても重要ですが、夢を叶えた後も戦いは続きます。
今回はJリーグに焦点を当て、
- Jリーグにおけるプロ選手の平均キャリア年数(引退までの寿命)
- 1人あたりの通算出場時間の平均
- 引退後のキャリア・就職先の実態
といった観点で掘り下げていきます。これからJリーガーを目指す若手選手や、すでにプロの世界に身を置いている選手はもちろん、サッカーファンの皆さん、さらにはスポーツ選手のセカンドキャリア問題に関心がある方にとって、少しでも有益な情報を提供できれば幸いです。
選手寿命の実態
平均して約6〜7年のキャリアが一般的
一般的に「プロの世界における選手寿命は短い」と言われていますが、Jリーグの例もまさにそうです。現役期間については、調査元や定義によって若干の違いはあるものの、平均で6〜7年ほどとする見解が多く見られます。
- Jリーグ元チェアマン・村井満氏による分析
かつてJリーグのチェアマンを務めた村井満氏によれば、Jリーグでプロ契約できる期間は平均6.3年程度とされています。さらに驚くべきことに、新人選手のうち約20%(5人に1人)は公式戦の出場機会がないままチームを去ってしまうという統計もあり、プロの厳しさを物語っています。
- 平均引退年齢は26歳前後
日本プロサッカー選手会やメディアの報道を総合すると、Jリーグの平均引退年齢は26歳前後とされることが多いです。高校卒業後にプロ入りした場合は5〜8年、大卒であれば3〜5年程度とさらに短くなる傾向にあります。
多くの人が「サッカー選手は30代で引退」というイメージを抱きがちですが、ベテランまで生き残るのはごく一部であり、大半の選手は20代で契約満了を迎え、別の進路を探す現実があるのです。
プロ野球と比較して
日本においてプロスポーツとして人気を二分するのは野球とサッカーですが、両者を比較すると、プロ野球選手の平均引退年齢が約29.8歳なのに対し、Jリーガーは約26歳という報告もあります。
野球では、投手と野手で細かい差はあるものの、全体としてサッカーよりキャリアが若干長いという統計が出ているようです。これはプレー形態の違いや下部組織の仕組み、または選手人口・資金力など複合的要因が考えられます。いずれにせよ、サッカーは走行距離や接触プレーの負荷が高く、体を酷使するスポーツでもあるため、平均的には引退が早くなるのは自然な流れかもしれません。
どれだけプロとして試合に出られるのか?
出場機会の厳しい現実
プロ選手としてデビューしても、実際に公式戦に「何分」出られるかはまた別の問題です。Jリーグの試合数は、J1リーグ戦で34試合+カップ戦や天皇杯などを合わせると年間40試合前後になります。ただし、そこでフル出場を重ねられる選手はごく一部。ベンチにも入れず、公式戦0分のまま契約満了となる選手が毎年一定数存在します。
- 新人選手の20%は公式戦出場なし
先述の通り、プロ入りしても初年度から試合に起用される選手は限られています。クラブによっては優勝争い、残留争いに追われ、実験的に若手を登用する余裕がないこともあるでしょう。さらに外国人枠や経験あるベテランの起用が優先される傾向もあり、若手にとっては競争が非常に激しいのです。
数千分単位で終わるケースが大半
Jリーグは1993年にスタートし、30年を超える歴史があります。通算で400試合以上(J1換算)に出場した“レジェンド”とも呼ばれる選手は数十名しかいません。日本代表クラスでも、長く在籍してようやく300〜400試合を超えるのが普通です。
- 歴代最多出場記録
たとえば大久保嘉人選手(現役引退)はJ1通算477試合出場でしたが、これは18年に渡るキャリアの積み重ねです。 - 多くの選手はJ1数十試合、もしくはJ2・J3含めても100試合未満でキャリアを終える
出場時間に換算すると、フル出場なら1試合で90分ですから、50試合でも4500分。つまり、数千分レベルでキャリアが終わる選手が多いと推測されます。
ベンチ要員・下位リーグ移籍も含めた総合的な見方
J1で出場機会を得られなければ、J2やJ3にレンタル移籍し、そこで試合経験を積む選手も珍しくありません。それでもレギュラーポジションを奪えない場合は、2〜3シーズンで契約満了となり、そのままプロを去る選手が後を絶ちません。
そのため、1人あたりの平均通算出場時間(Jリーグ全体でどれだけの分数をプレーしたか)を厳密に出すのは難しいのが現状です。ただ、大多数の選手は数十試合(数千分)の出場機会しか得られないという見方が有力です。フル出場を続けて通算1万分、2万分を超える選手となれば、それは“成功した部類”と言えるでしょう。
引退後のキャリア
サッカー界に留まる選手が約2/3
引退後の進路に関して、日本プロサッカー選手会(JPFA)や各種メディアのアンケートによれば、引退後の元Jリーガーのうち半数以上(約2/3)はサッカー界に留まるというデータがあります。具体的には以下のような道が挙げられます。
- クラブの指導者やスタッフ
アカデミー(ユースやジュニアユース)のコーチや育成組織の責任者、トップチームのコーチ、GKコーチ、通訳、スカウトなど、多岐にわたります。かつて同じクラブの選手として活躍した“OB”がコーチに就任し、そのまま指導者ライセンスの取得を目指すケースが代表的です。 - サッカー解説者・メディア出演
テレビやインターネット番組、スポーツ紙などで解説者や評論家として活動する例もあります。特に日本代表クラスの知名度が高い選手はこの道を選びやすいと言われます。 - 地域サッカースクールの経営・指導
自身の地元などでサッカースクールを立ち上げ、子供たちにサッカーを教える仕事に就くことも一般的です。プロ時代の知名度やネットワークを活かし、地元スポンサーからのサポートを得てスクール運営を軌道に乗せるケースもあります。
ただし、上記のように関わりご飯を食べていけるのはJリーグで結果を残したTOPの選手のみでしょう。
それ以外の選手は結果として一般企業への就職・転身が多いようです。
プロになるのは難しい、生き残るのはもっと難しい
ここまで、Jリーグにおけるプロサッカー選手の現役寿命や出場時間の実態、そして引退後の仕事・収入にまつわる現状を見てきました。総括すると、以下のようなポイントが浮かび上がります。
- Jリーガーの現役寿命は約6〜7年程度と非常に短い
契約満了や戦力外通告によって早期に現役を断念するケースが多く、引退年齢は26歳前後と若い水準です。ベテランまで生き残れるのはごく一部。 - 1人あたりの通算出場時間は数千分が平均的
新人の約2割は公式戦ゼロ出場でチームを去るほど競争が激しく、多くの選手が数十試合前後の出場機会しか得られません。 - 引退後の進路は「サッカー界に留まる」か「一般企業へ転身」が中心
全体の約2/3はコーチやスタッフ、メディアなどサッカー関連の仕事を選び、残り約1/3が異業種への転職や起業など別の道を歩みます。ただし個々のポジションにつけるのもごく一部
こうした厳しい現実を踏まえると、Jリーガーを目指す若手は「短期決戦」であることを自覚し、可能な限り早い段階でセカンドキャリアに備える必要があるとも言えます。
もちろん現役選手である以上、目の前の試合や練習に集中するのが最優先ですが、怪我やチーム事情など何が起こるかわからない世界です。少なくとも「引退後は何をするか」「どんな勉強や資格取得が必要か」を意識し始めることが大切でしょう。
夢を目指すことはもちろん重要です。しかしながらこのような【いばらの道】だということを十分念頭に置いておく必要があります。
プロになるのは難しい、生き残るのはもっと難しいという言葉を忘れず日々精進していきましょう!!

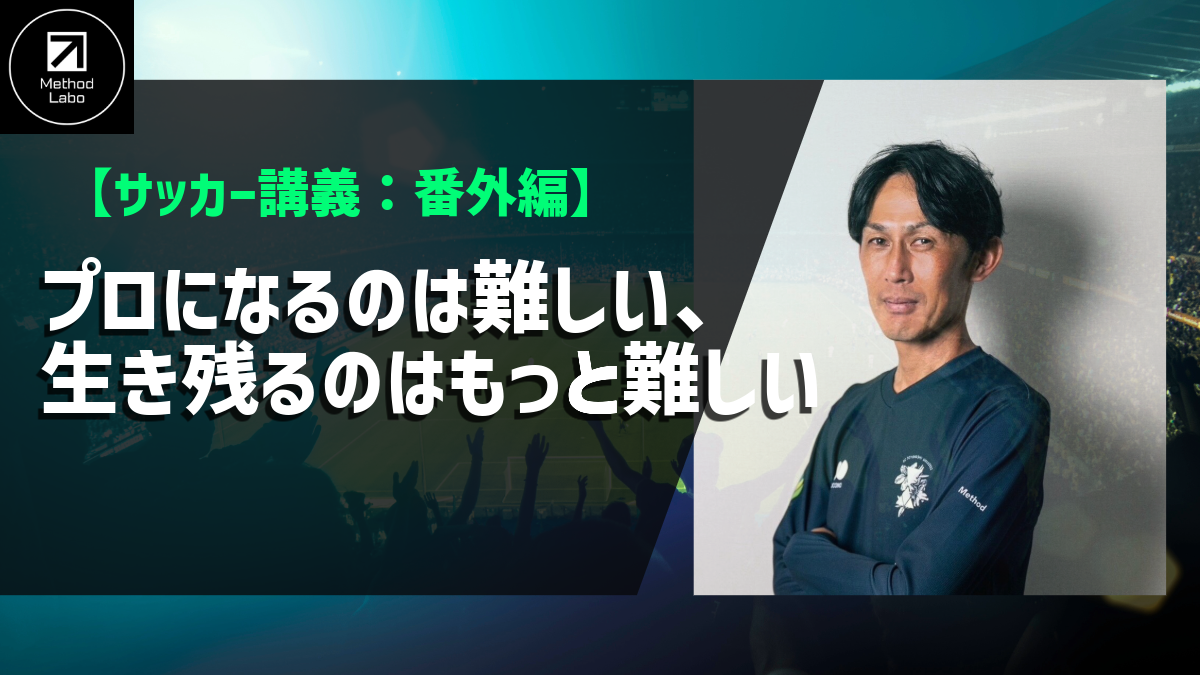
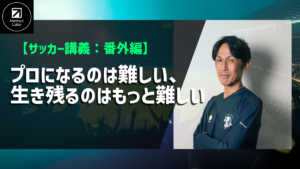








コメント