はじめに
現代サッカーにおいては年々ビルドアップに注目が集まっていると考えています。我々メソッドラボのサイトでも【ビルドアップ】をテーマにした記事が人気です。
「ビルドアップは、チームが相手エリアに前進するための方法として、現代サッカーにおいてはとても重要です。」というと語弊が生まれますが、ボールを大事に保持しながら効果的に前進し、攻撃の起点を作るための「プロセス」としてとても重要であり、ビルドアップの成功はを試合を優位に進める可能性を上げます。
ビルドアップは一見するとリスクが高い前進の手段にも思えます。しかしながらその一方で強豪クラブの多くがビルドアップを重視し、試合を優位に進めるために活用していることも事実です。
本記事では、ビルドアップの目的・リスクを中心に解説します。現代サッカーでなぜこれほど「ビルドアップ」という言葉が熱いのか、そしてその目的とリスクについて一緒に理解を深めていきましょう。
高まる「ビルドアップ」の重要性
かつては最終ラインから長いボールを蹴り込んで相手陣地へ素早く押し込み、セカンドボールを奪い合うスタイルが主流だった時代もありました。
しかし現代では、ゴールキーパーやディフェンスを含めた“11人全員での攻撃”が求められる風潮が強くなっています。加えてゴールキック時のルール改正(ペナルティエリア内での味方へのパスが可能になった)によって、ゴールキーパーを含む「後方からの組み立て」が格段にやりやすくなったように思えます。
ビルドアップが注目される理由としては、単に「ボールを保持する」というだけでなく、相手の守備陣を動かしズレを生み、最終的に高い位置(相手陣深く)まで数的優位あるいはスペースの優位性を確保しながら攻め込むというメリットがあるからです。
サッカーでは“相手を動かして、スペースを作り出す”ことが大切です。これを果たすために後方で落ち着いてボールを回し、徐々に前進することで最終的に前線(相手陣内)で有利な状況を生みやすくなるわけです。
とはいえ、一部の考えとして「リスクを冒してまで後ろからつなぐ必要はあるのか?」という声も依然として根強く存在します。ロングボールを使ってシンプルに自陣を脱却する戦い方も十分あり得るからです。よって、「ビルドアップをどう活用するか」が指導者の思考の見せ所であり、それによってパターンやプレーモデルが多く存在するのだと考えています。
ビルドアップの特徴
数的優位を活かしやすい
ビルドアップの最大の特徴は、ゴールキーパーをも含めた11人でのパスワークにあります。相手ゴールキーパーが守備に直接参加しない以上、攻撃側が数的優位を作りやすい状況となるのです。
たとえば4-4-2や4-3-3で前線からプレスをかける相手でも、後方に3~4人のパス回し役を配置してしまえば、相手最前線の守備では全員をケアしきれない瞬間が生まれます。そのフリーの選手を起点に相手ラインを突破し前進していけば、数的優位な状況を保ちつつ、ゴールへ迫る効果的な攻撃につなげられるわけです
相手をおびきだしズレを生む
後方からパス回しを丁寧に行うことで、相手を前へ引き出す“誘導”の役割も担います。自陣深くでボールを保持すると、相手は奪いに来るために前線からプレスをかけざるを得ません。
そこを狙って、空いた中盤やサイドに展開することで相手のラインにズレが生じ数的優位や空いたスペースを利用して前進できる可能性が上がります。
後方の選手のスキル
よって近年、ゴールキーパーやディフェンス陣にも足元の技術や正確なパスが強く求められるようになりました。守備的ポジションに求められる能力はかつてのような“単純に守るだけ”ではなく、「いかに攻撃を始められるか」に比重が移っています。ビルドアップが注目される背景には「後方の選手たちの攻撃面での貢献度が飛躍的に上がった」ことも大きく関係していると考えます。
ビルドアップの目的:なぜ後方から組み立てるのか
ここで改めて、ビルドアップが持つ主な目的を整理しておきましょう。特に以下の三つは欠かせないポイントだと考えています。
安全確実にボールと人を前進させる
ディフェンスラインやゴールキーパーから徐々にパスをつなぎ、チーム全体を押し上げながら攻撃の起点を作ること。相手陣内まで効率良く持ち込むためには、選手同士のコミュニケーション・距離間、立ち位置や技術力が不可欠です。むやみにロングボールを多用して相手に回収されるリスクを減らしつつ、確実にボールを前線へ届けるという考え方がビルドアップの軸にあります。
相手陣内深くにボールを有利に進める
ビルドアップを行う際には、単純に後ろでボールを回すだけでは意味がありません。最終的には「ゴールを奪う」ことが目的です。中盤やサイド、あるいは相手のギャップを突いてスペースにボールを運び、前線の選手が仕掛けやすい状況を作ることが大切です。ビルドアップはあくまでも、【数的優位を作りゴールを奪うまでの“プロセス”】と指導者と選手が理解することで、ただ保持するだけの“ボール回し”に陥ることを防ぎやすくなります。
一か八かの確率をできるだけ下げる
ロングボールばかりだと、ボールが常に落ち着つかず「50:50」の状況が続きます。そこで競り負けてしまい。セカンドボールが拾えなかった場合は相手にカウンターを許すなど、一気に形勢が変わるリスクがあります。
これを最小限にするための方法がビルドアップです。ビルドアップで複数のパスコースを確保しながら段階的に相手守備陣を揺さぶり前進していきます。もちろんビルドアップ自体にもリスクは伴いますが、チーム全体の戦術理解度や選手の判断力・技術が上がれば得点機会と確率を増やすことができ、失点の機会を減らすことが可能です。
ビルドアップのリスク
一方、ビルドアップには当然ながらリスクも存在します。特に以下のような点は、どのカテゴリーでも悩みの種になるでしょう。
プレスがかわしきれないとハマる
対戦相手は前線からの積極的なプレス、あるいは特定の選手へのプレスを増やしてビルドアップを防いでくるでしょう。高校サッカーなどでロングボールを選択するチームが多いのは、無理にビルドアップに拘って相手の激しいプレスを受け失点してしまう確率を下げるためです。結局単調なロングボールの試合が多くなる傾向にあります。
特に“ブラインドキック”と呼ばれるような判断を伴わない長いボールで、相手が予測できない状況を作る方がシンプルかつ効果的なことが多いからです。
自陣ゴール前でミスするとショートカウンターを許す
ロスト(ボールを失う)する場所が自陣深い位置であればあるほど、相手のショートカウンターを許す危険度が高まります。Jリーグや欧州のトップリーグでも、GKやCBのちょっとしたトラップミスが失点に直結する場面は珍しくありません。
チーム全体の連携が整っていないと崩壊
ビルドアップは“組織的な連動”がとても大切です。選手同士で同じ絵を描けていないと、パスコースが噛み合わず、簡単にインターセプトを許してしまいます。また、足元の技術に不安がある選手が後方にいる場合、相手に狙い撃ちされてしまいかねません。
ボール保持が目的化してゴールを目指さなくなる
「後ろからつなぐこと」と考えすぎると、いつの間にか本来のゴール奪取よりもボール保持自体が目的になってしまうケースがあります。相手を揺さぶってこそビルドアップは意味を持つのであって、ただパスを回すだけでは得点機会を増やせず、逆にリスクだけが積み重なる恐れもあります
ビルドアップにこだわって陥りがちな失敗
戦術的なメリットが大きいとはいえ、ビルドアップに過度にこだわりすぎると、以下のような失敗に陥る可能性があります。
無理なパス回しによるミスが失点を招く
最終ラインやゴールキーパーの足元技術が高くない状態で、相手の強度の高いプレスを受け続けると、致命的なパスミスが起こりやすくなります。高校サッカーでは特に、守備的選手の負担が大きくなるケースが顕著です。
攻撃の“仕掛けスイッチ”を入れ忘れる
ビルドアップの目的はあくまで“ゴールを奪うためのプロセス”です。しかし、保持ばかりに意識が向くと、肝心の攻撃スイッチを入れるタイミングを失ってしまう恐れがあります。ゴールに直結するパスや仕掛けを見極める判断力が、ビルドアップ重視のチームには不可欠です。
まとめ
現代においては、ゴールキーパーやディフェンダーが“フィールドプレーヤー並み”の足元技術を持つことも珍しくなく、そうした能力を最大限に活かすためにビルドアップが活用されるケースが増えています。一方で、リスク管理や相手のプレスへの対応が欠かせない戦術でもあるため、チーム全体の連携や状況判断力が試される場面が多いのも事実です。
世界のトップクラブ同士の対戦では、お互いがビルドアップを駆使しつつ、それを阻止しようとするハイプレスを激しくぶつけ合う、ハイレベルな“読み合い”が繰り広げられます。今後はさらに、ゴールキーパーがどこまで攻撃参加を行うのか、センターバックやボランチがどれだけ攻撃のスイッチを入れられるといった点が注目されるでしょう。
重要なのは「状況に応じた柔軟な対応」です。ビルドアップという手段にこだわりすぎて、チームの特徴や選手の能力を無視してしまえば本末転倒。時にはロングボールを効果的に使い、前線のターゲットを活かすことも必要です。
ビルドアップはあくまで“攻撃へ移行するためのプロセス”であり、試合状況や相手の守備対応に合わせて使い分けることこそが重要だと我々は考えています。
改めて強調したいのは「ビルドアップは手段であって、目的そのものではない」という点です。最終的にはゴールを奪うことがサッカーの本質であり、勝利に直結するためにビルドアップを取り入れるのであって、ビルドアップ自体を絶対視する必要はありません。指導者が“なぜビルドアップを採用するのか”を明確にし、そのリスクとメリットを正しく理解することで、皆さんの戦術に深みが増すはずです。
何かの参考になれば幸いです。

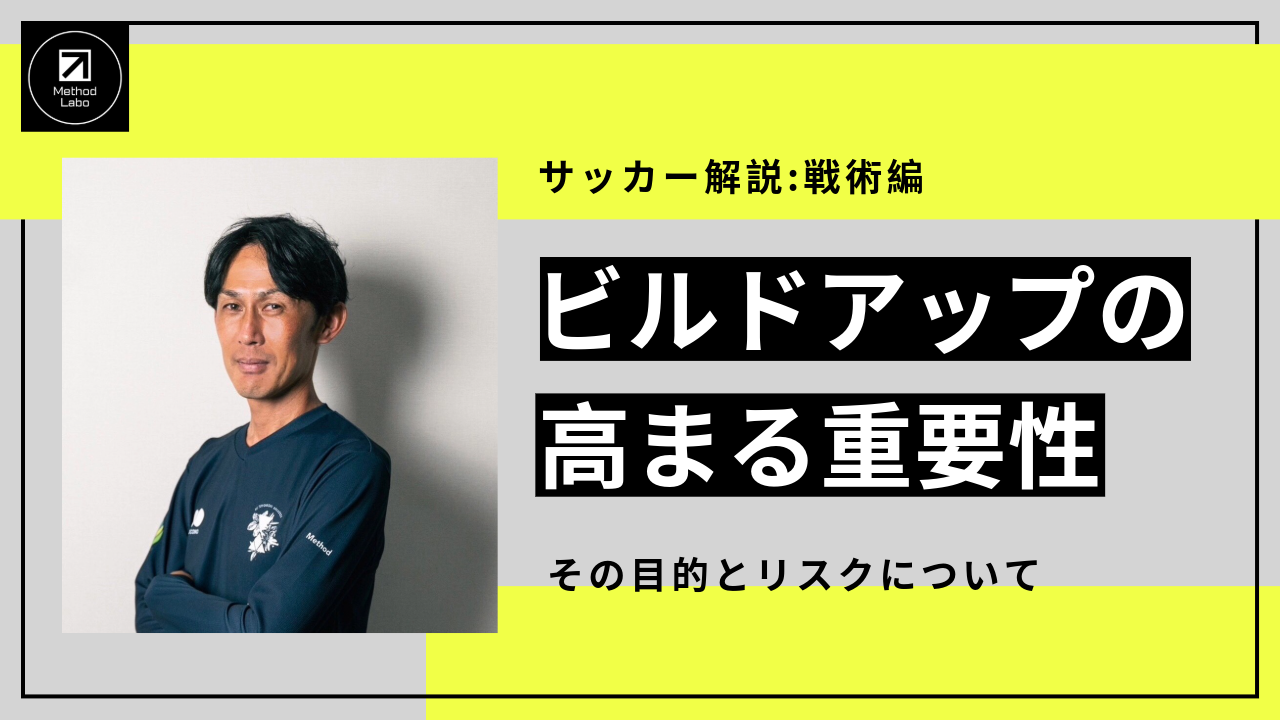
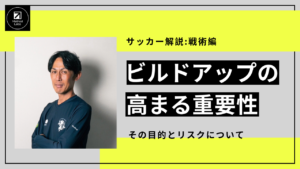
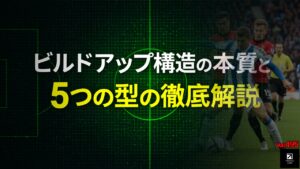







コメント