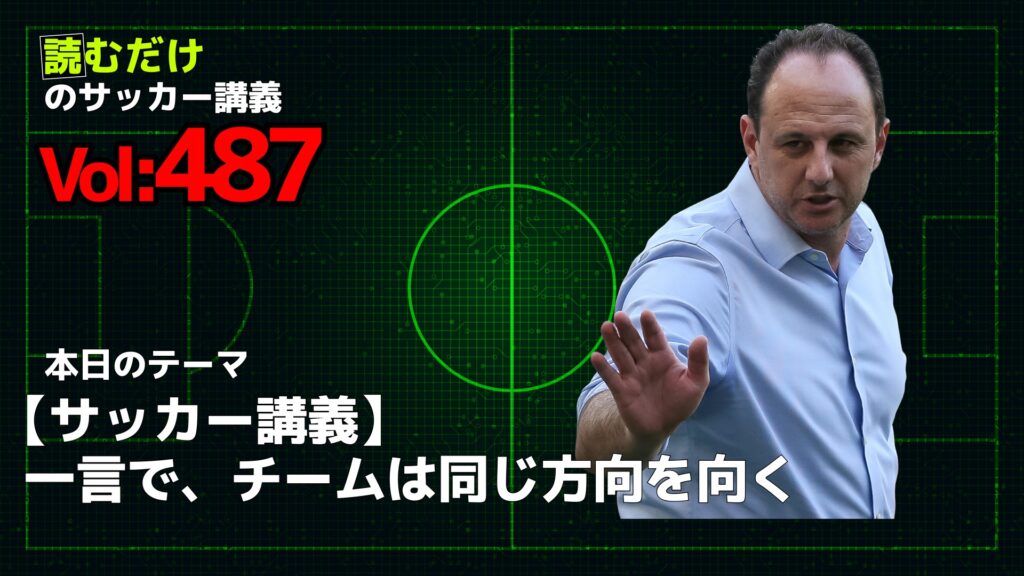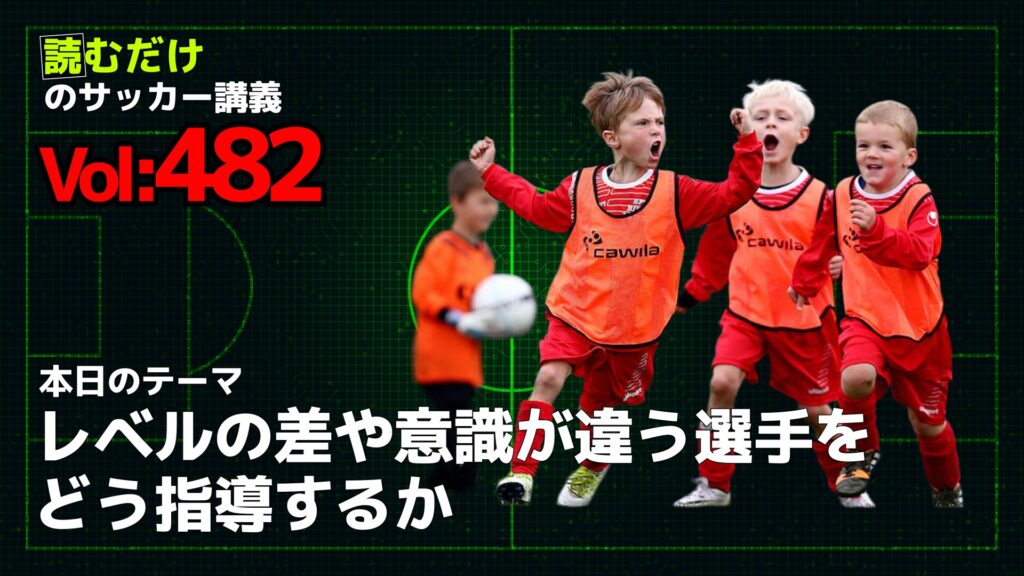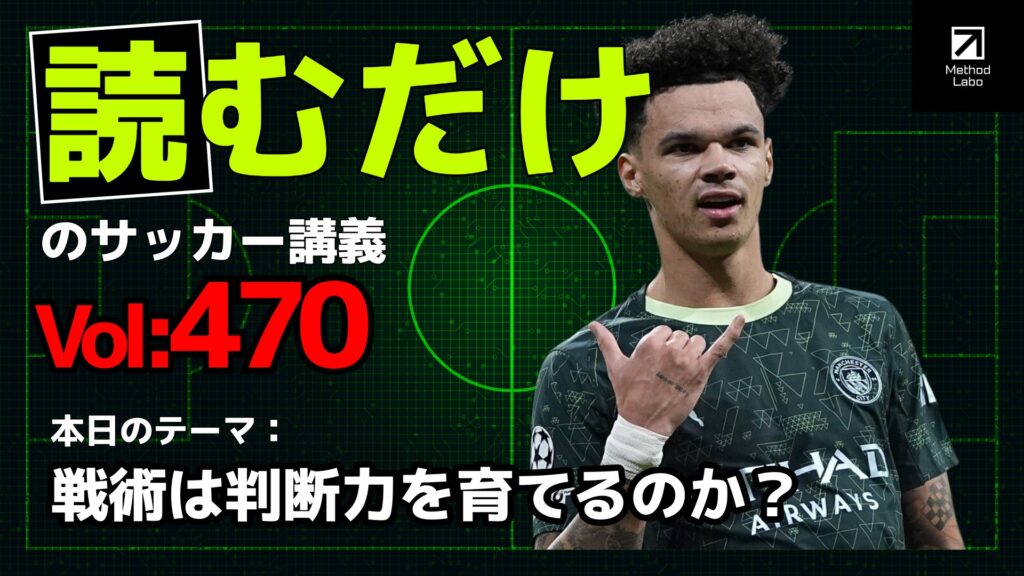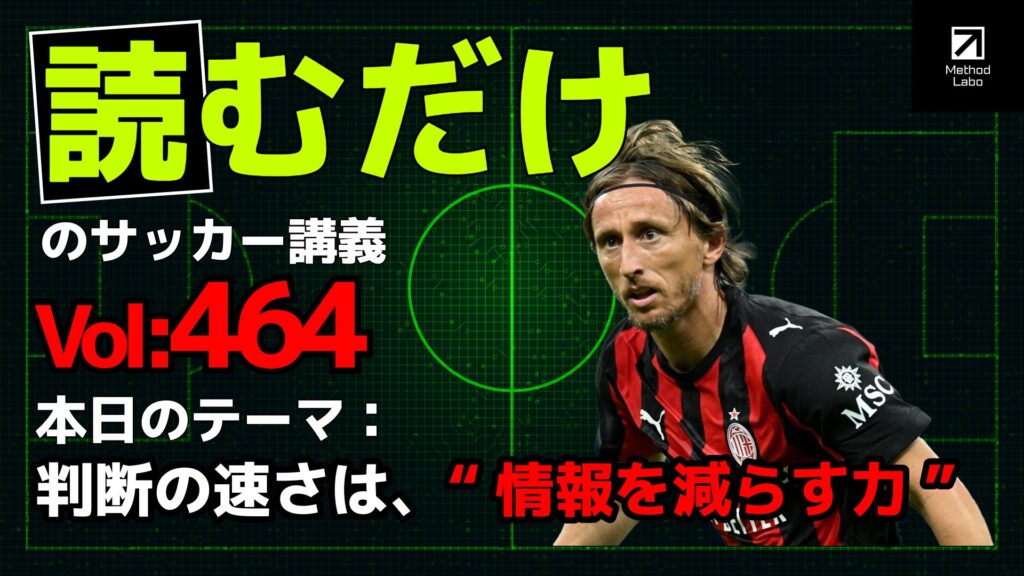指導哲学/考え方– category –
-

【サッカー講義】第3GKの葛藤:その心境にあなたはどんな言葉をかけるか?
――ピッチの外で戦い続ける、もう一人のゴールキーパー―― サッカーチームにおいて、「第3GK」という立場ほど、難しく、そして語られにくい役割はないかもしれません。 試合に出る可能性は極めて低い。大会方式によってベンチに入れることもありますが、アッ... -

【サッカー講義】一言で、チームは同じ方向を向く
――ブラジェビッチ監督の「傘」に学ぶ、戦術言語の力―― 1998年フランスW杯。 クロアチア代表を3位に導いたミロスラヴ・ブラジェビッチ監督のチーム戦術は、今なお語り継がれています。モドリッチが登場する以前のクロアチアが世界を驚かせた理由は、個の才... -

【サッカー講義】私がビルドアップ時に大切にしていること
――「前進するため」ではなく、「主導権を握るため」に―― ビルドアップという言葉を聞くと、「後ろからつなぐこと」「パスを回すこと」と捉えられがちです。しかし、私がビルドアップで最も大切にしているのは、単にボールを前に運ぶことそのものではありま... -

【サッカー講義】強さと人間性は両立する。神村学園が見せた「リスペクト」の力
第104回全国高等学校サッカー選手権大会は、神村学園の優勝で幕を閉じました。大会を通して見せた彼らのサッカーは、技術、フィジカル、戦術理解のどれを取ってもハイレベルでした。しかし私の心に最も強く残ったのは、プレーの質以上に人としての振る舞い... -

【サッカー講義】パスの目的 〜ボールを動かせ!と言っても上手くいかない本当の理由〜
――「ボールを動かす」では、相手は動かない サッカーにおいて「パス」は最も基本的なプレーの一つです。練習でも試合でも、私たちは日常的にこう声をかけます。 「もっとボールを動かそう」 「パスを回そう」 「テンポよくつなごう」 しかし、その言葉通り... -

【サッカー講義】レベルの差や意識が違う選手を、どう指導するか
――「同じトレーニング × 違う観点」がチームを育てる サッカーの指導現場で、多くの指導者が直面する悩みがあります。それは、「レベルの差」や「意識の差」をどう扱うか、という問題です。 同じトレーニングをしていても、すぐに理解し実行できる選手がい... -

【サッカー講義】トレーニングでゴールや「ゴール方向」を設定した方が良い時、しない方が良い時
すべては「目的」から逆算する サッカーのトレーニングを設計するとき、必ずと言っていいほど出てくる問いがあります。「この練習には、ゴールを置くべきか。それとも置かないべきか」 一見すると単純な選択のようですが、実はここにトレーニングの質を大... -

【サッカー講義】サッカー指導における「差別化」の大切さ
――選ばれるチーム、育つ選手を作るための“軸”―― サッカー指導の現場では、多くの指導者が似たようなトレーニングメニューを用い、同じような言葉を使い、似たようなアプローチを取ってしまいがちです。しかし、現代サッカーがこれほど高度化し、情報があふ... -

【サッカー講義】「戦術があるから判断が育つ」という考えは誤っているのか?
――“教え込む”指導から、“環境”で育てる指導へ―― 「戦術があるからこそ、選手の判断が育つ」と我々は考えています。 確かに、戦術的な枠組み(フレームワーク)は、選手にプレーの方向性を示し、チームとしての共通理解を育むために不可欠な要素です。しか... -

判断の速さは、“情報を減らす力”で決まる――サッカーにおける思考の断捨離
サッカーにおいて「判断の速さ」は、優れた選手の条件として必ずと言っていいほど挙げられる能力です。ボールを受けてからの一瞬のひらめき、スペースを見つける速さ、相手の動きを読む洞察力。こうした能力は、一見すると「頭の回転が速い」とか「天性の...