はじめに
【サッカー選手になりたい!】これは多くの子どもが一度は描くものかもしれません。ですが、実際にプロとして活躍できるのはほんの一握り。「生まれ持った才能がないと無理」と言われてしまうこともあるでしょう。もちろん才能が重要だということは認めます。
しかし、数々のプロ選手の歩みを振り返ると、決して天才だけが成功しているわけではないことがわかります。そして過去天才を言われた選手がすぐに引退してしまういった事実もあります。
プロになる選手の幼少期の育ち方や日々のトレーニング、そして強靱なメンタルを支える家族や指導者の存在……。そういった要素が複合的に混ざり合い積み重なった結果として、プロとしてデビューできたのでしょう。今回は「プロサッカー選手になる人に共通する4つのポイント」を一旦整理して伝えていきます。
幼少期の育ち方や環境
プロサッカー選手の多くが口をそろえて語るのは、幼少期の“自由な遊び”の経験です。まだ少年団に所属する前の年齢から、外でボールを蹴って楽しむ時間が長かったり、近所の公園で友達や兄弟、時には年上の子に混ざってサッカーをしていたりと、ルールに縛られない遊びを通じて自然にボールコントロールや判断力を身につけていくケースが多く見られます。
特に年上相手にプレーしていたという選手が多いように感じます。
体格差やスピード差をものともせず自分なりに戦う術を見つけざるを得なくなり、結果的に独創性が磨かれ負けず嫌いになっていったと考えられます。
さらに、家の中でも常にボールを触れる環境づくりを意識している家庭もあるようです。「サッカーに没頭できる環境」をさりげなく整えておくことがサポートする側としては大事なのかもしれません。子どもが主体的にサッカーを楽しめるように配慮しているわけです。
一方で、幼いころから「プロを目指すのだから、あれもこれもやらせよう」と過度に大人が管理しすぎると、子ども自身がサッカーを純粋に楽しむ気持ちを失いがちです。多くのプロ選手はむしろ「気づけばサッカーをしていた」「夢中でボールを蹴っていた」という自然なスタートを振り返ります。こうした経験が、サッカー選手になる土台となっていると考えられます。
練習に向き合う姿勢
ただ量をこなすだけでなく、「どうすればもっと上手くなるか」を常に考えながら練習しているのもポイントです。ときには自分のプレーを録画して見直す、上手い選手の技術を真似して分析するなど、自主的に工夫を凝らしている人が多くいます。
特筆すべきは、意外にも天才肌と思われる選手ほど“地道な反復練習”を大切にしている点です。利き足ばかりでなく逆足のキックを徹底的に練習したり、基礎的なリフティングやトラップを毎日欠かさず続けたりする姿がたびたび語られています。こうした地味な練習の積み重ねが、大事な試合での正確なプレーや会場を沸かせるような瞬間を生む基礎となっているわけです。
また、練習を“楽しめる”かどうかも重要です。外から見ると膨大な練習時間に見えても、当の本人は「サッカーが好きで好きでたまらないから、練習時間をつい長く取ってしまう」と語ります。好きだから没頭でき、没頭するうちに技術や身体能力が伸びていくのは、ある意味で理想的な成長サイクルと言えます。もちろん、必ずしも毎日が楽しいだけではなく、挫折やスランプに陥ることもありますが、それでも根底には「サッカーが好き」という気持ちがあるからこそ、練習を続けられるのでしょう。
思考法
メンタル面を語るうえで外せないキーワードが「逆算思考」と「創意工夫」です。明確な目標を掲げ、その達成に向けて今何をすべきかを逆算する。その結果、日々の練習や試合で必要となる努力が浮き彫りになり、ただ闇雲に頑張るのではなく「自分には何が足りないのか」「どうすればもっと得点できるのか」と問題を具体化し、自分なりの創意工夫で解決に取り組む姿勢も見逃せません。
逆境への強さも共通点として挙げられます。例えば小柄な体格で評価されずに挫折を味わった選手が、どうやって一度離れたサッカーに再び向き合ったか。あるいは周囲が天才だらけのチームに飛び込んで、練習試合すらろくに出られなかった選手が、どうやって自分の居場所を確立していったか。そこには共通して「強みと弱みを把握して対策を続ける」「仲間や指導者のアドバイスを素直に受け入れる」といった柔軟な姿勢があります。
さらに、チームスポーツである以上“協調性”も鍵です。どれだけ個人技が優れていても、仲間を尊重しない姿勢ではプロの舞台で長く活躍することは難しいでしょう。ゴールを決める選手がいれば、アシストする選手がいる。守備を支える選手がいれば、そこから攻撃につなぐ選手がいる。プロになるには仲間とのコミュニケーションや周囲への気遣いが欠かせません。「ひとりでは結果を出せない」ことを意識することで、チームへの貢献を最優先に考えるメンタルが磨かれていくのです。
(エゴであることは重要だが、自分勝手になってはならない)
周囲のサポート
プロ選手のインタビューを追うと、家族や指導者の存在が大きな力になっているエピソードが頻繁に登場します。例えば、子どもがサッカーに熱中できるようあえて口出ししすぎない親のスタンス。「外遊びを存分にさせ、ケガや失敗も含めて学ばせる」という姿勢は、子どもの主体性を培ううえで極めて重要です。ときには親自身もサッカーに打ち込んだ経験がなくても、“一緒にやってみる”ことで親子のコミュニケーションが深まると同時に、子どもは自分の好きなことを親も理解してくれていると感じ、安心感を得るのです。
また、良き指導者との出会いはサッカー人生を大きく左右します。勝利至上主義で子どもに過度なプレッシャーを与える指導者も存在する一方、本当に必要なのは選手の成長と人格形成を同時に考えた指導です。(しかし勝ちたい…葛藤は常にあります)実際、トップレベルの選手たちは「自分を否定せずに長所を伸ばそうとしてくれる指導者」に出会ったタイミングで飛躍的に能力を伸ばしていることが少なくありません。ある指導者の何気ない一言が自信につながり、ポジション適正を見抜いてもらったことで才能が開花するという事例も多く見られます。
家庭やチームメイトに恵まれていなくても、本人が諦めない限り成長は続きます。しかし、周囲の温かいサポートや適切なアドバイスがあれば、遠回りせずに自分の道を切り開くことができるのも事実。プロになった選手はそうした環境に感謝し全力を尽くしているのエピソードが印象です。
プロになるための4要素が相乗効果を生む
ここまで見てきたように、1)幼少期の環境、2)練習に向かう姿勢、3)思考法、4)サポート環境は、複合的に作用しています。例えば、幼少期の自由な遊びが「サッカーって楽しい」という原体験がモチベーションになり膨大な練習量を支える。あるいは、小さな成功体験の積み重ねで得た自信が逆境を乗り越えるメンタルを育む。
才能は確かに魅力的ですが、そればかりに注目してしまうと本質を見失いがちです。実際にプロの舞台に立っている選手の中には「もともと無名だった」「ジュニアユースで最後のほうの立ち位置だった」という人も少なくありません。彼らが口をそろえて言うのは、「特別な才能がなくても、正しい努力を継続すればプロになれる可能性は十分にある」という希望に満ちたメッセージです。
まとめ:すべては“サッカーが好き”から始まる
もちろん、勝負の世界は甘くありません。厳しい競争に勝ち続けなければプロの地位を維持できないのが現実です。だからこそ、土台となるのは“サッカーが好き”という純粋な思い。どれほどキツい練習や試合でも、「好きだからこそ乗り越えられる」という強いモチベーションが必要なのです。多くの選手にとって、この“サッカー愛”が挫折を乗り越える原動力であり、プロとして長期的に活躍する秘訣でもあります。
好きだからこそ努力し、努力するなかで技術が伸び、技術が伸びるとさらにサッカーが楽しくなり……という上昇スパイラルが生まれます。反対に、どれだけ周囲に才能を評価されていても、本人がサッカー自体を楽しめない状況が続けば、成長は頭打ちになってしまうでしょう。
プロサッカー選手になる人々の共通点は、単に“生まれながらの才能”ではありません。幼少期にのびのびとボールを蹴れる環境と、主体的に練習を楽しむ姿勢。逆境に負けず目標を逆算して努力を続けるメンタルと、一人ひとりの個性を伸ばす家族や指導者のサポート。それらが絡み合ってこそ、プロへの道が開けます。
我々は「もっと上手くなりたい」「試合に勝ちたい」という純粋な欲求を伸ばしてあげることが重要です。いずれにせよ、子どもが自分自身の可能性を追求できるよう応援することこそが本質的なサポートであり、ひいては“好き”を形にする大きな力になるのです。
今回の4つの要素、是非参考にしてみてください。

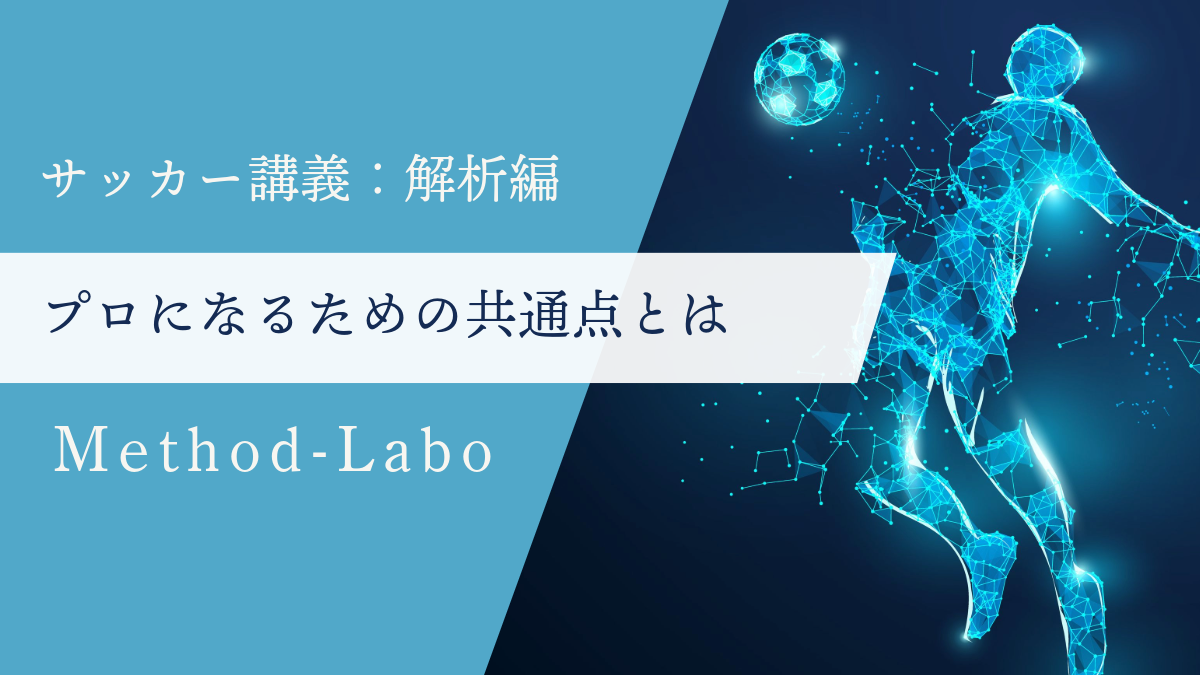









コメント