はじめに
サッカーで注目すべきは「速さ」だけではありません。むしろ、その逆。一流の選手たちが意図的に作り出す、一瞬の“間・静寂”にこそ、試合を支配する鍵が隠されています。
その名は「パウサ」。
今回はパウサとは何か、なぜ重要なのか、そして、いかにして選手たちはこの技術を駆使しているのかを解説していきます。
この記事を読み終える頃には、ピッチ上で繰り広げられる静かなる駆け引きに気づき、サッカー観戦に新たな着眼点を加えてくれるはずです。
サッカーにおける「パウサ」の正体とは?
まず、「パウサ」という言葉の基本的な意味から理解を深めていきましょう。
パウサの語源と本質的な定義
「パウサ」とは、スペイン語で「休止」「小休止」を意味する言葉です。サッカーにおいては、ボールを持った選手が、あえてプレーのスピードを緩め、意図的に“間(ま)”や“タメ”を作るプレーを指します。
これは単に疲れて休んでいるのでも、次に何をすべきか迷っているのでもありません。むしろその逆で、極めて高度な状況判断と技術に裏打ちされた、戦術的な一時停止なのです。
特に、繊細なボールタッチと戦術的思考を重んじる南米やスペインのサッカー文化において、パウサは古くから選手の価値を測る重要な指標とされてきました。それは、単なる個人技ではなく、チーム全体を機能させるための潤滑油であり、ゲームの流れをコントロールするための重要な要素だからです。
なぜ「間」が必要なのか? – パウサが持つ4つの戦略的目的
では、なぜ選手たちはピッチの上で意図的に“止まる”のでしょうか。その目的は、大きく分けて4つあります。
- プレーのリズムを鎮静化させる 激しいプレスの応酬や、カウンターの応酬が続くと、試合は選手たちの思考が単調になりやすい高速な展開になります。このような混沌とした状況で、パウサは一度ゲームを落ち着かせ、チームに冷静さを取り戻させる効果があります。
- 味方のための時間を創出する 攻撃は、一人の選手だけで完結するものではありません。サイドバックが駆け上がる時間、フォワードが裏へ走り出す時間、中盤の選手がサポートに入る時間。パウサは、これらの味方の動きを“待つ”ための貴重な時間を作り出します。ボールを保持し、相手を引きつけることで、味方が最適なポジションを取る猶予を生み、攻撃の厚みと連動性を高めるのです。
- 相手守備組織を崩す 守備側の選手は、ボールホルダーの動きを予測してポジションを取ります。「パスが出る」「ドリブルで仕掛けてくる」といった予測のリズムの中で、パウサによる一瞬の“停止”は、そのリズムを完璧に崩します。
守備者は「あれ?」と足が止まったり、焦れて食いついてきたりします。その瞬間に生まれたわずかなズレやスペースこそ、決定的なパスやドリブルが成功するための突破口となるのです。
- 試合の主導権を掌握する サッカーの試合は、ボールの保持率だけでなく、「テンポ」の支配権をどちらが握るかが極めて重要です。パウサを自在に操れる選手がいるチームは、速攻と遅攻を意のままに使い分け、試合のテンポをコントロールできます。相手を走らせて疲れさせたり、自分たちのペースで試合を進めたりと、ゲーム全体の主導権を握るための強力な武器となるのです。
パウサがもたらす戦術的アドバンテージ
パウサの基本的な目的を理解したところで、次はその効果が具体的にどのような戦術的アドバンテージを生み出すのかを、より深く掘り下げていきましょう。全部で4つあります。
攻撃のテンポを自在に操る指揮官
優れた司令塔は、指揮官のごとくゲームのテンポを操ります。パウサは、まさにその指揮棒の役割を果たします。例えば、自陣でボールを奪い、カウンターを発動する場面。相手の守備陣形が整う前に素早く攻めたいのがセオリーです。しかし、ここで一人の選手がハーフライン付近で巧みにパウサを使うとどうなるでしょうか。
前線の選手はフリーランニングのコースを探す時間を、後方の選手は攻撃参加の時間を手に入れます。相手守備陣は、速攻を警戒して後退すべきか、ボールホルダーにプレスをかけるべきか、一瞬の判断を迫られます。この迷いこそが、より確実で、より破壊力のある攻撃パターンを生み出すのです。速攻の中に意図的なパウサを挟むことで、攻撃の選択肢は無限に広がります。
つづきは明日(2025/8/3)更新予定の【後編】でお楽しみください。

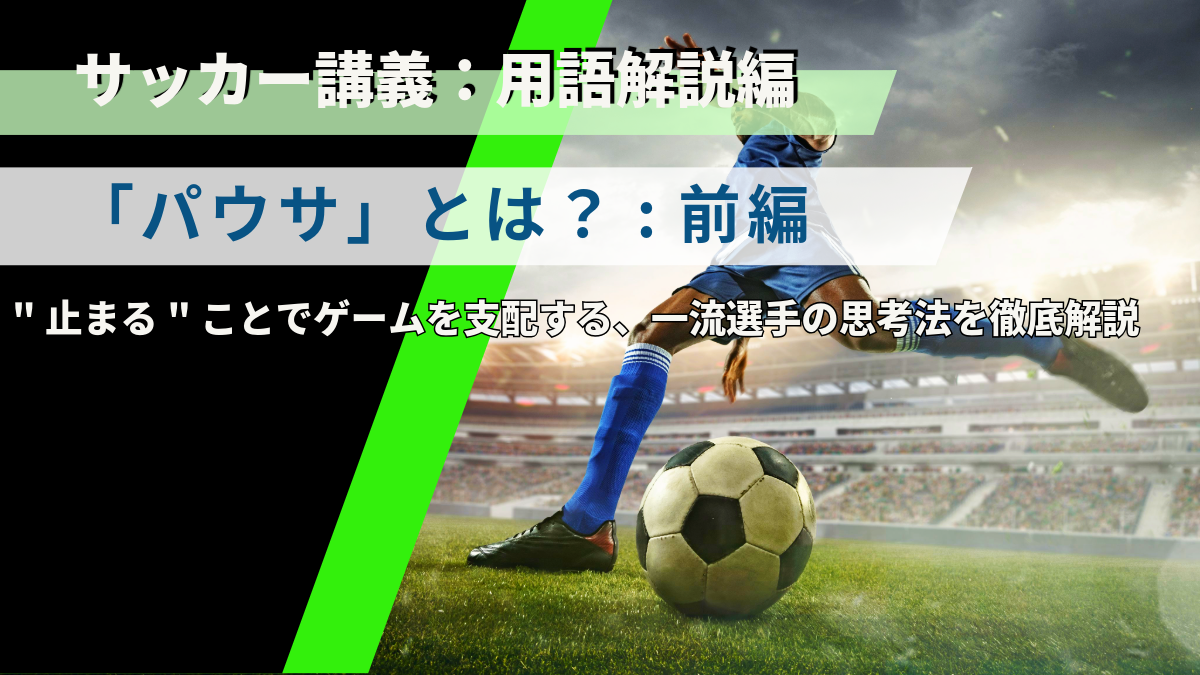
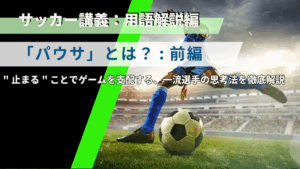








コメント