サッカーの戦術は絶えず進化を続けています。特に、2024-25シーズンにかけてのヨーロッパでは、監督たちの緻密な思考が反映された、いくつかの明確な戦術トレンドが見られます。
かつてのような固定されたフォーメーションや単一のプレースタイルに固執するのではなく、より流動的で、より強度の高い、そしてより知的なアプローチが主流となりつつあります。
今回は現在のヨーロッパサッカーを席巻している7つの主要な戦術トレンドをキーワードとして抽出し、それぞれの内容、メリット、そしてなぜそのような流れが生まれているのか、その背景までを記事にまとめました。
ハイプレッシング/カウンタープレッシング
まずはこれですね。ゲーゲンプレスとも言えます。
ボールを失った直後に、即座に複数の選手が連動して相手に激しいプレッシャーをかけ、ボールを奪い返す守備戦術です。目的は、相手にビルドアップの時間を与えず、可能な限り敵陣の高い位置でボールを奪取し、ショートカウンターに繋げることにあります。
この戦術の最大のメリットは、相手の攻撃の芽を早い段階で摘むことができる点と、相手ゴールに近い位置で攻撃の起点を作り出せる点です。一方で、チーム全体が前方に大きなエネルギーを費やすため、選手の身体的な消耗が激しく、一度プレスを突破されてしまうと、自陣の守備が手薄になり、広大なスペースを突かれるというリスクも伴います。
ポジショナルプレーとゾーン
ポジショナルプレーとは、選手たちがそれぞれ定められたゾーン(位置)でプレーすることを基本とし、チーム全体で最適なバランスを保ちながらボールを動かすことで、相手を意図的に動かし、スペースを作り・活用する攻撃戦術です。ピッチ上に常に三角形のパスコースが確保されるよう、選手たちはボールの位置に応じてポジショニングを微調整し続けます。
この戦術のメリットは、ボール保持率を高め、試合の主導権を握りやすい点にあります。相手を自陣から引き出し、その背後に生まれたスペースを計画的に利用することができます。しかし、選手間の距離が広がりすぎると(間延びすると)、パスが繋がらずボールを失う原因となったり、相手が引いて守備ブロックを固めてきた場合には、効果的な攻め手を見つけられずに手詰まりになったりする課題もあります。FCバルセロナやマンチェスター・シティ、フェイエノールトなどが、この戦術の代表的な実践チームとして知られています。
ハイブリッドなフォーメーション(可変システム)
これは、試合の状況に応じて、チームのフォーメーションや選手の役割を動的に変化させる、極めて流動的な戦術コンセプトです。例えば、試合開始時の基本布陣は4-2-3-1であっても、ボールを保持した攻撃時には、サイドバックの一人が中盤に入るなどして3-2-5のような形に変化し、守備時にはまた別の布陣に戻るといった形です。
この戦術の最大のメリットは、相手チームにとってプレーの予測が非常に困難になり、守備の基準点を乱してギャップを作りやすい点にあります。ただし、これを実行するためには、選手一人ひとりに極めて高い戦術理解度と、複数の役割をこなせる技術が求められます。選手間の連携が少しでも崩れると、ポジショニングの乱れから非効率なプレーが増えるリスクも抱えています。マンチェスター・シティやアーセナル、パリ・サンジェルマンといったトップクラブで、この流動的な戦術が顕著に見られます。
バック3/ウィングバック活用
守備ラインを3人のセンターバックで構成し、両サイドの広いエリアをウイングバック(WB)が担当するシステムです。攻撃時には、このウイングバックが高い位置を取ってピッチの幅を確保し、攻撃に厚みをもたらします。守備時には、ウイングバックが最終ラインまで下がることで、5バックに近い堅固な守備ブロックを形成します。
このシステムのメリットは、攻撃時の幅の確保と、守備時の中央の安定性を両立できる点にあります。攻守の切り替えもスムーズに行いやすいのが特徴です。その一方で、攻守両面で広大なエリアをカバーするウイングバックには、極めて高い運動能力と多様なタスクをこなす能力が要求され、選手への負担が非常に大きいという側面もあります。インテル・ミラノやブライトンなどが、この戦術を効果的に用いる代表的なチームです。
カウンター & トランジション
これは、自陣で守備を固め、相手の攻撃が終わった瞬間や、相手がプレッシングに出てきた裏のスペースを狙い、素早く縦方向への攻撃でゴールに迫る戦術です。ボールを奪ってから相手ゴールへ到達するまでの時間を、可能な限り短縮することを目的とします。
この戦術のメリットは、相手の守備陣形が整っていない、最も無防備な時間帯を突くことができるため、極めて効果の高い決定機を作り出せる点にあります。しかし、攻撃への切り替えを急ぐあまり、ボールをすぐに失ってしまうと、逆に相手からカウンターを受けるリスクも高まります。プレミアリーグなど、試合展開の速いリーグでは、このトランジション(攻守の切り替え)の局面からの得点、いわゆる「ファストブレイク」が増加傾向にあります。
“ボックスミッドフィールド”(中央のオーバーロード)
これは、攻撃時に中盤の中央エリアに4人の選手を集中させて「箱(ボックス)」のような形を作ることで、ピッチの中央で数的優位を作り出す戦術です。この中央での密集により、相手の守備者を引きつけ、その脇や背後にスペースを生み出させたり、選手間の短いパス交換で相手のプレスを剥がしたりすることを狙います。
メリットは、チームの心臓部である中央エリアでパスコースが増え、ライン間でボールを受ける動きが活性化される点にあります。しかし、中央に人数をかける分、サイドエリアが手薄になる可能性があり、相手が中央を徹底的に封鎖する守備戦術を取ってきた場合には、攻撃が停滞するリスクもあります。
セットプレー
コーナーキックやフリーキックといったセットプレーを、単なる偶然のチャンスではなく、再現性の高い得点源として位置づけ、そのデザインを高度に洗練させるトレンドです
メリットは、試合の流れに関わらず、平等に与えられるチャンスから得点を奪える可能性が高まることです。拮抗した試合において、流れを変える決定的な一撃となることも少なくありません。ただし、守備側も同様にセットプレーを分析・研究してくるため、常に新しいデザインを生み出し、相手との読み合いに勝つ必要があります。アトレティコ・マドリードなどは、伝統的にセットプレーからの得点が多いクラブとして知られています。
まとめ
これらの戦術トレンドが生まれてきている背景には、いくつかの複合的な要因が存在します。
第一に、選手の能力の進化が挙げられます。現代のトッププレイヤーは、高い身体能力と技術に加え、優れた戦術理解力を兼ね備えています。これにより、一人の選手が複数のポジションや役割をこなすことが可能になり、監督は試合中にフォーメーションを変化させるような、より複雑な戦術を採用しやすくなりました。
第二に、データ分析(アナリティクス)の進化です。現代のクラブでは、専門のアナリストが膨大な試合データを分析し、「どのエリアでボールを奪われやすいか」「どの攻撃ルートが得点確率が高いか」といった情報を、極めて詳細に導き出します。監督たちは、これらの客観的なデータに基づいて戦術を構築し、より効率的で合理的なプレーモデルを追求するようになっています。
第三に、戦術の多様化への対応です。対戦相手もまた、様々な戦術を駆使してきます。一つの戦い方に固執するのではなく、相手のシステムや試合展開に応じて、自らの戦い方を柔軟に変化させられる能力が、現代の監督には不可欠となっています。
そして最後に、ゲームスピードそのものの高速化も大きな要因です。プレミアリーグやラ・リーガといったトップリーグでは、攻守の切り替えの速さが勝敗を分ける決定的な要素となっています。相手の守備が整っていない状況をいかにして突くか、という発想が一般的となり、育成年代からそうした戦術教育が進んできていることも、全体のゲームスピードを加速させている一因と考えられます。


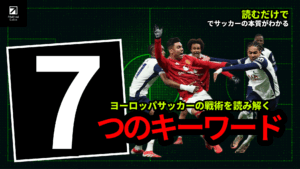
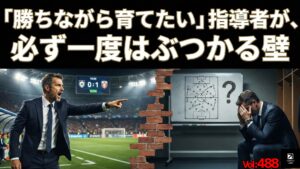


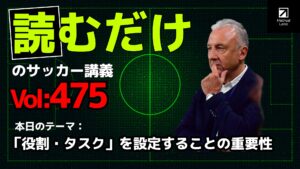
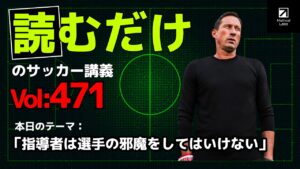

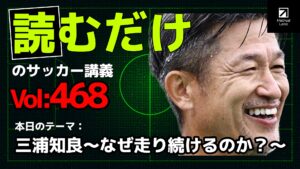

コメント