前回の続きからになります。
まだ前編をご覧になってない方はこちらからご確認ください。
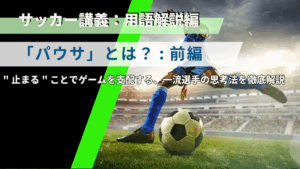
パウサがもたらす戦術的アドバンテージ
相手を“釣る”巧妙な罠
パウサは、相手守備陣を動かすための「釣り」にもなります。守備者は常にボールとマークする相手を視野に入れ、次のプレーを予測しています。ボールホルダーがドリブルの体勢に入れば、対応する準備をします。パスを出しそうな素振りを見せれば、パスコースを消しにかかります。
ここでパウサが使われると、守備側の予測は外れる可能性が高まります。例えば、パスを出そうとモーションに入りながら、一瞬止まる。すると、パスコースを消そうと動いたDFの背後に新たなスペースが生まれます。その瞬間を狙って、スルーパスを送り込む。
これは、守備の隙を突く、極めて高度なプレーです。相手が動くのを「見てから」プレーを選択できるため、後出しジャンケンで勝負しているようなものであり、圧倒的な優位性を生み出します。
思考をする時間を作る
トップレベルの試合では、選手に与えられる時間とスペースはごくわずかです。絶えず周囲からプレッシャーを受ける中で、最善の判断を下し続けることは至難の業です。
しかし、パウサを体得している選手は、ボールを自分の支配下に置くことで、物理的な時間だけでなく、思考のための時間をも生み出します。ボールを足元に置き、一瞬スピードを緩めることで、顔を上げてピッチ全体を見渡す余裕が生まれます。
このコンマ数秒の間に、味方の走り込み、相手DFのポジション、GKの位置といった膨大な情報をインプットし処理するのです。その結果、誰も予測しなかったような創造的なパスや、相手の意表を突くプレー選択が可能になります。パウサは、複雑な局面を解きほぐし、思考する時間を創出します。
試合の“呼吸”を整えるセーフティネット
どんな強豪チームにも、試合の中で何をやってもうまくいかない苦しい時間帯は訪れるものです。パスはつながらず、シュートは枠を外れ、相手のカウンターを浴び続ける。このような「負のスパイラル」に陥った時、流れを断ち切るのがパウサの役割です。
一人の選手が中盤でボールを落ち着かせ、ゆっくりと時間を使い、チーム全体の呼吸を整える。これにより、パニックに陥っていたチームは冷静さを取り戻し、戦術を再確認する時間を得ます。無理な攻撃によるミスや、安易なボールロストからのカウンターを防ぐセーフティネットとして機能し、チームを崩壊から救うのです。
歴史に名を刻む「パウサ」の使いたち
名選手たちのプレーの中にほぼ確実にパウサが見られます。
アルゼンチンの伝統が生んだ司令塔「エンガンチェ」
パウサを語る上で欠かせないのが、アルゼンチンサッカーにおける「エンガンチェ」というポジションの存在です。トップ下に君臨し、攻撃の全権を握る司令塔を指すこの役割の選手たちです。
その象徴的存在が、ファン・ロマン・リケルメです。彼は決して俊足ではありませんでしたが、ボールを持てば誰も彼からボールを奪うことはできませんでした。絶妙なボールの置き所と、相手の逆を突くタイミングでパウサを使い、まるで時を止めたかのように中盤に君臨。彼のタメ一つで、チーム全体の攻撃のリズムが生まれ、数々の決定機が演出されました。
リオネル・メッシ
現代最高の選手、リオネル・メッシもまた、パウサを駆使する天才です。彼のパウサは、特にドリブルの最中に顕著に現れます。相手DFと対峙した瞬間、彼は一瞬“止まり”ます。この静止によって、DFは次の動きを予測できずに足を止めてしまいます。そして、DFの重心が固まった瞬間、メッシは爆発的な加速で抜き去るか、あるいは逆サイドの味方へ完璧なパスを供給するのです。
アンドレス・イニエスタ
FCバルセロナの黄金期を支え、ヴィッセル神戸のファンをも魅了したアンドレス・イニエスタは、「パウサの教科書」とも呼ばれる選手です。彼のプレーの特徴は、ボールを受けた際の独特な“タメ”にあります。プレッシャーを受けても慌てず、ボールをさらしながら相手を引きつけ、味方が動き出すための完璧な時間を作り出します。彼のパウサは、周囲の選手をより輝かせるためのものであり、彼がいるだけでチームのパスワークは滑らかに、そして相手にとって脅威になりました。
新時代の継承者、ペドリ
バルセロナのDNAを受け継ぐ若き才能、ペドリもまた、若くしてパウサの感覚を身につけた稀有な選手です。狭いエリアでボールを受けても決して失わず、落ち着き払ったプレーで中盤をコントロールします。彼のプレーを見ていると、イニエスタやシャビといった偉大な先人たちの哲学が、確かに次世代へと受け継がれていることを感じさせます。
日本サッカーと「パウサ」
世界の名手たちが見せるパウサ。では、我々の日本サッカーにおけるパウサの現状はどうなっているのでしょうか。
イニエスタが投じた一石 – 「日本のサッカーにはパウサがない」
このテーマを語る上で避けては通れないのが、前述のアンドレス・イニエスタがJリーグに来日した当初に語ったとされる、*日本のサッカーにはパウサがない」という有名な言葉です。これは、日本の選手やサッカーを批判したものではなく、文化的な違いを的確に指摘したものでした。
日本のサッカーは伝統的に、勤勉さ、組織力、そしてスピードを重視してきました。最後まで走り切る献身性、規律の取れた守備、そしてボールを奪ってからの素早い攻撃(堅守速攻)は、日本サッカーの大きな武器です。
しかし、意図的にプレーを遅らせる、“止まる”という選択肢が文化として根付きにくかった側面は否めません。育成年代から「判断を早く」「シンプルにプレーしろ」と指導されることが多く、ボールを持って考える時間、つまりパウサの重要性が見過ごされがちだったのです。
パウサを感じさせる日本人選手たち
しかし、近年その状況は大きく変わりつつあります。多くの選手がヨーロッパのトップリーグでプレーするようになり、世界のスタンダードを肌で感じる中で、パウサの重要性を理解し、体現する選手たちが現れ始めました。
- 久保建英: スペインで育った彼は、パウサの概念を最も自然に体得している日本人選手の一人です。ドリブルの途中で急にスピードを落としたり、一瞬止まって相手を引きつけたりするプレーは、まさに“間”の駆け引きそのものです。彼のプレーからは、常に複数の選択肢を持ちながら、相手の動きを見て最善手を選ぶ知性を感じさせます。
- 鎌田大地: トップ下やインサイドハーフでプレーする彼は、攻撃の最終段階で決定的な違いを生み出すパウサの使い手です。ペナルティエリア手前でボールを持った際に、無理に仕掛けずに一瞬タメを作ることで、走り込んでくる味方へのラストパスの精度を高めたり、相手DFの陣形に乱れを生じさせたりします。
- 三笘薫: 彼の代名詞は爆発的なスピードのドリブルですが、その凄みは単なる速さだけではありません。ドリブルの過程で巧みに緩急をつけ、相手DFの前で一瞬“止まる”ことで、相手の足を完全に止めさせます。そして、相手が体勢を立て直す前に、一気にトップスピードで抜き去るのです。彼のドリブルは、パウサを最高の形で活用したものです。
- 田中碧: 中盤の底でゲームを組み立てる彼は、派手さはないものの、極めて高い戦術眼を持っています。ボールを持った際に決して慌てず、常に顔を上げて周囲を認知し、的確なパウサで攻撃のテンポを調整します。彼の落ち着きが、チームに安定感と攻撃の起点をもたらしています。
「止まる勇気」
これらの選手たちの活躍は、日本サッカーが新たなステージに進むための重要な鍵を握っています。ワールドカップでベスト8以上の成績を目指す上で、単にスピードと組織力で戦うだけでなく、試合をコントロールし、ゲームの流れを支配する能力は不可欠です。
そのために必要なのが、「止まる勇気」です。
常に前へ、速く、という意識から一歩踏み出し、あえて止まることでより良い選択肢を探す。その勇気が、個々のプレーの幅を広げ、ひいてはチーム全体の戦術的な成熟度を高めることにつながるでしょう。
サッカー観戦をより楽しくする「パウサ」への注目
ここまで、サッカーにおける「パウサ」という概念について、その定義から戦術的な価値、名手たちのプレー、そして日本サッカーとの関係性までを深く掘り下げてきました。
パウサとは、単なるボールキープの技術ではありません。それは、時間と空間を支配するための高度な戦術的思考であり、選手のサッカーIQが凝縮されたプレーです。
ピッチ上で繰り広げられる、目には見えない静かなる駆け引きこそが、サッカーというスポーツの奥深さを象徴しています。
ぜひボールを持つ選手の一瞬の“停止”に注目してみてください。
「なぜ、彼は今ここで止まったのか?」
「その一瞬の間に、ピッチ上では何が起きていたのか?」
「あの“間”が、次のプレーにどう繋がったのか?」
そこ隠された意図を読み解こうとすることが、サッカー観戦が何倍も知的なものになり、より奥深いものになるでしょう。

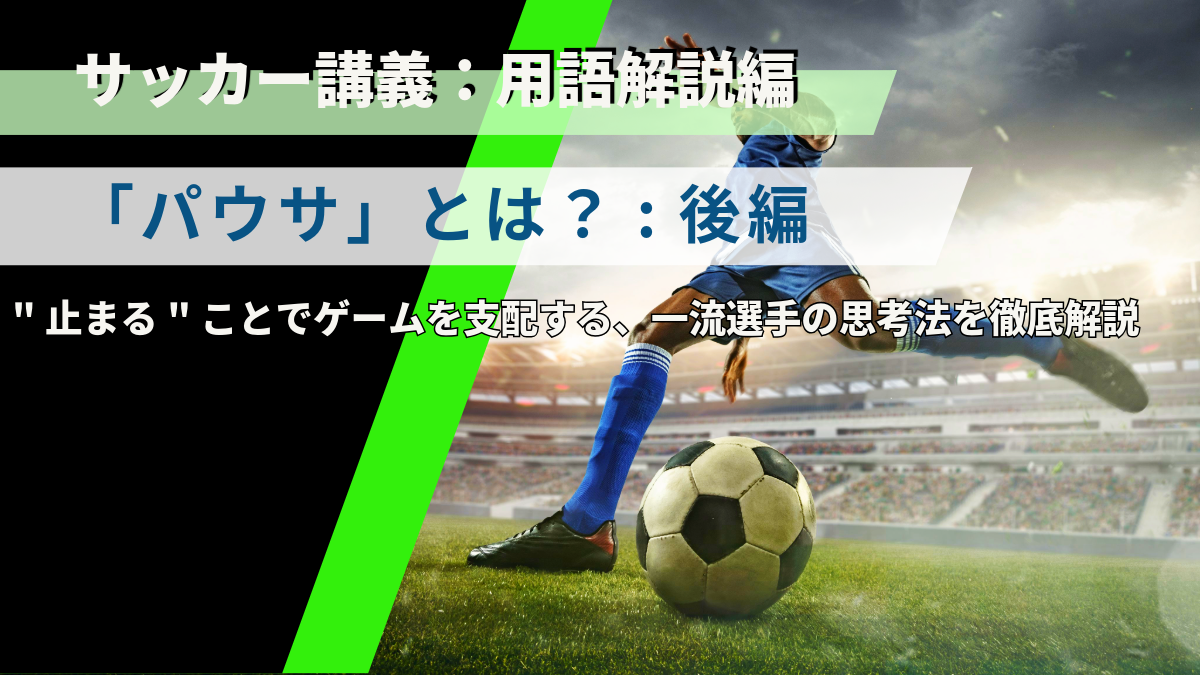
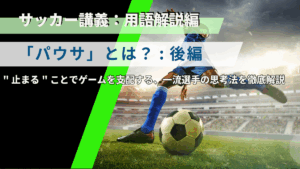








コメント