前編の続きからになります。
まだご覧になっていない方は以下の続きからご覧ください。
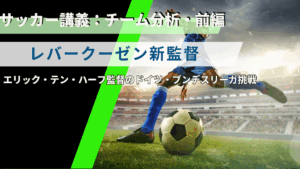
守備戦術の原則 ― いかにしてゴールを守るのか?
彼のチームの土台には常に徹底的な規律に裏打ちされた堅固な守備組織があります。
中盤でのブロック形成とコース遮断 彼の守備の基本は、中盤でブロックを形成するディェンスです。最優先事項は、中央を固め、相手のアンカーやトップ下といった危険な選手へのパスコースを遮断すること。むやみにボールホルダーへ飛び込むのではなく、組織として連動し、相手に効果的なパスを入れさせないことを徹底します。
「即時奪回」とダブルボランチの器用 ボールを失った瞬間の切り替え(トランジション)の速さも、彼が選手に強く求める要素です。ボールに最も近い選手が即座にプレッシャーをかけ、周囲が連動してパスコースを限定し、ボールを奪い返す。この組織的な即時奪回が、失点のリスクを減らすと同時に、ショートカウンターへの起点にもなるのです。またダブルボランチを採用することに攻守にわたってワンボランチの負担を軽減しています。
現代の名将たちとの比較 ― テン・ハーフはどこが違うのか?
テン・ハーフは理想と現実のバランスを取りながら、「選手の特性に応じた戦術の最適化」を進めていました。選手の役割を明確にしながら、構造的に修正していく姿勢は、まさに「支え、引き出し、育てる」哲学の実践版とも言えます。私も参考にさせていただいている場面が多いです。
彼の戦術的立ち位置をより明確にするために、ミケル・アルテタ(アーセナル)とロベルト・デ・ゼルビ(マルセイユ)と比較してみましょう。
| 監督 | 戦術スタイルの核 | ビルドアップ | 守備戦術 | 柔軟性 |
| テン・ハーフ | 現実主義的ポゼッション | 3バック化+GK起点 | 中盤ブロック+即時奪回 | 高い(相手に応じて変化) |
| アルテタ | ポジショナル+左右非対称 | 偽SBで中盤を厚く | ハイプレス+ゾーン | 中程度(試合中の修正) |
| デ・ゼルビ | 疑似カウンター+徹底ポゼッション | レイオフパスで相手を誘導 | マンツーマン+高ライン | 高い(相手の構造に対応) |
vs アルテタ
アルテタ監督は、グアルディオラ譲りの厳格なポジショナルプレーを「構造主義」です。選手の立ち位置を定め、システムの中で選手の役割を明確にします。一方、テン・ハーフ監督は、選手の特性や試合状況に応じてシステム自体を変化させる。アルテタが「システムに選手を適合させる」傾向があるのに対し、テン・ハーフは「選手の特性に応じてシステムを最適化する」プローチを取ります。
vs デ・ゼルビ
デ・ゼルビ監督のビルドアップは、意図的に相手のプレスを「釣り出す(誘導する)」ことを目的とした、極めて高度なものです。低い位置でリスクを冒してでもボールを保持し、相手が食いついてきた背後のスペースを狙います。対してテン・ハーフ監督のビルドアップは、より「安定性」を重視します。3バック化などで後方に数的優位を作り、リスクを最小限に抑えながら着実にボールを前進させることを優先します。
レバークーゼンで花開くか?テン・ハーフの新たな挑戦
根底にある「支え、引き出し、育てる」という哲学は、クラブの構造を改善していく上で非常に価値のあるものです。この経験を糧に、ブンデスリーガという新たな舞台で、彼の戦術がどのように進化し、レバークーゼンの選手たちと融合していくのか。そのプロセスを見守ることは、最大の楽しみの一つとなるでしょう。
監督の哲学や戦術的な狙いに目を向けることで、ピッチ上で起こる一つ一つのプレーの意味が深まり、サッカーはより知的なスポーツとして我々の前に姿を現します。エリック・テン・ハーフの新たな挑戦から、今シーズンも目が離せません。

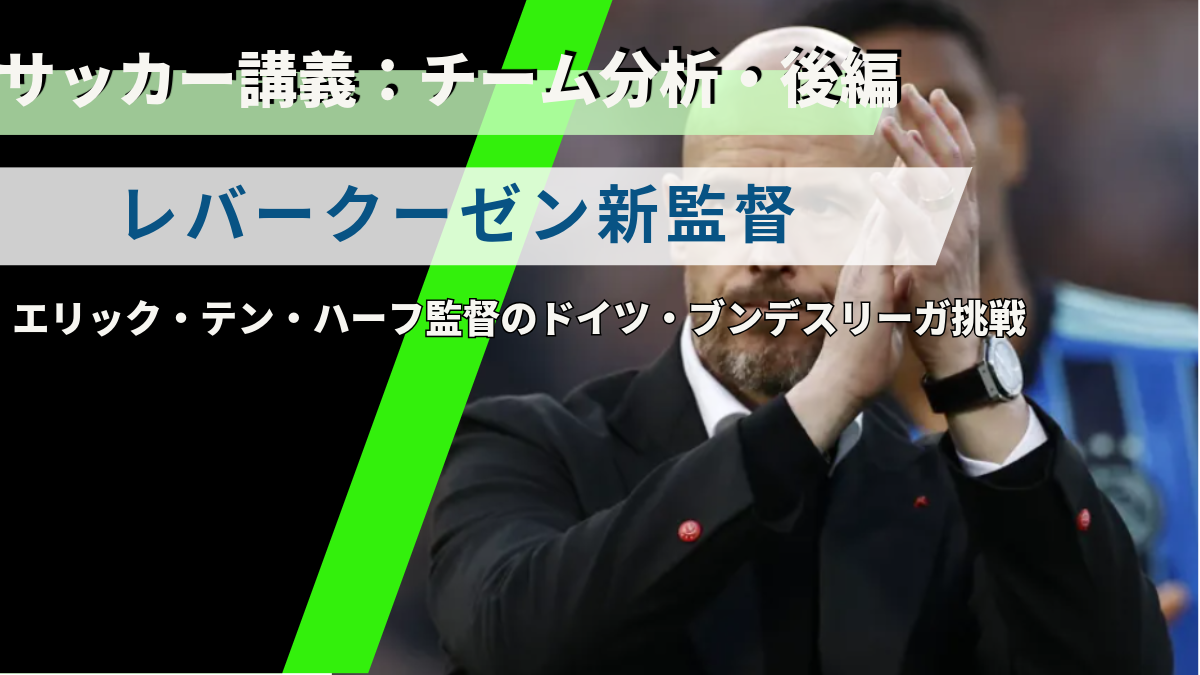
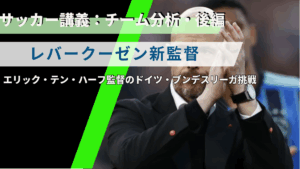








コメント