なぜ、プロ経験のない私がサポートを始めたか
「もっと声を出せ!」「集中しろ!」「気持ちで負けるな!」
サッカーの指導現場、特に育成年代のピッチサイドに立つと、今でもこうした声が、まるで義務であるかのように飛び交っているのを耳にします。
もちろん、選手を鼓舞し、チームの士気を高める上で、こうした言葉が持つ力を否定するつもりはありません。しかし、その声だけが支配するグラウンドに、私はどこか息苦しさを感じずにはいられませんでした。その言葉の裏側で、声の出し方が分からずにうつむく選手はいないだろうか。プレッシャーに押しつぶされ、本来のプレーを見失っている選手はいないだろうか。指導者の熱意が、時として選手の心を置き去りにしてはいないだろうか。
技術を教え、戦術を授ける。それは指導者の重要な役割です。しかし、どれだけ戦術論を語り、高度な技術を実演してみせても、選手の心が閉ざされていては、その言葉は決して届きません。
私自身、長年にわたり指導者として活動する中で、技術や戦術の探求だけでは決して辿り着けない領域があることを痛感してきました。それは、選手の「心」の問題であり、指導者と選手、あるいは指導者自身の内面における「対話」の問題です。
プロサッカー選手でもなければ、Jリーグのクラブを率いた経験もありません。そんな私が、なぜ個人のサッカー観や指導論を発信し、さらには最前線で奮闘する指導者たちをサポートするという、一見回り道にも思える活動を続けるのか。
それは、サッカーというスポーツが、そして人の成長というものが、決してピッチ上のプレーだけで完結するものではないという、確信にも似た想いがあるからです。
私が指導者のサポートという道を選んだのか、その根源にある問題意識と哲学、そして日本のサッカー界の未来に向けたささやかな願いを、包み隠さずお伝えしたいと思います。
発信することの重要性――思考は言葉にすることで磨かれる
私の活動の根幹には、「発信する」という行為があります。ウェブサイトやSNSを通じて、戦術論やコーチングに関する考えを日々発信し続けています。この行為は、単に知識をひけらかしたり、一方的に何かを教えたりするためではありません。それは、私自身にとって不可欠な「学びのプロセス」であり、サッカー界全体へ貢献だと考えているからです
思考を外へ:なぜ私はサッカー論を発信するのか
指導者としての日々の中で、頭の中には常に漠然としたアイデアや仮説、あるいは言語化できない課題意識が渦巻いています。「今日の練習の、あの現象は何だったのだろう」「この戦術を、どうすれば選手たちに分かりやすく伝えられるだろうか」。こうした内なる問いは、頭の中だけでこね繰り返しているだけでは、いつまで経っても形となりません。
しかし、それを「書く」という行為、つまり言葉にして外へ出すことで、思考は初めて客観的な形を持ち始めます。自分の考えを他者に伝わるように論理的に組み立て、適切な言葉を探すプロセスは、そのまま自分自身の思考を整理し、深めるための自己との対話となるのです。発信とは、他者へ向けているようで、実は何よりもまず、自分自身の学びのために行っているのです。
他者との対話による成長
発信された意見は、読んだ人の数だけ異なる受け取られ方をし、時には賛同や共感、時には批判や疑問となって私のもとへ返ってきます。私は、この「フィードバック」こそが、思考を磨き上げる上で最も重要な触媒であると考えています。
自分一人では決して気づけなかった視点、考えもしなかった角度からの問いかけ。そうした他者からの刺激に触れることで、自分の考えの正しさを再確認したり、あるいはその脆さに気づかされたりします。自分の意見が絶対ではないと知ること、多様な価値観を受け入れることは、指導者として偏屈な考えに陥らないために不可欠な姿勢です。発信は、私を常に謙虚な学び手でいさせてくれる、貴重な機会なのです。
かつての自分へ
私がこのような活動を続ける、もう一つの大きな原動力。それは、指導者として歩み始めたばかりの頃の、過去の自分自身の姿です。当時は、目の前の選手たちのために何ができるのか、どうすればもっと良い指導ができるのかと、暗中模索の日々でした。
練習メニューの組み方、選手とのコミュニケーション、戦術の勉強法。知りたいこと、学びたいことは山ほどあるのに、身近に相談できる相手や、指針となるような情報を得られる場所は、決して多くはありませんでした。
「もし、あの頃の自分がこのような発信の機会または情報に触れることができたら・・・」。
を考えることは多々あります。私のささやかな経験や、試行錯誤の末に得た知識が、かつての私と同じように悩む、どこかの誰かの役に立つかもしれない。
たった一人でもいいので、「この考え方がヒントになった」「少しだけ視界が晴れた」と感じてくれる人がいるのなら、発信を続ける価値は十分にあります。それは、未来のサッカー界への貢献という大袈裟なものではなく、同じ道を歩む同志への知識のシェア、そんな感覚に近いのかもしれません。
技術だけでは勝てない時代のコーチング
思考を発信し、他者と対話する中で、私の問題意識は次第に一つの核心へと収斂していきました。それは、現代のサッカー、特に育成年代において、選手を本当に成長させるために必要なのは、もはや技術や戦術の指導だけではない、ということです。
指導現場の「息苦しさ」の正体
冒頭で触れた「声を出せ!」という言葉に象徴されるように、日本の指導現場には、いまだに精神論や一方的な指示に偏重する文化が根強く残っています。もちろん、それは指導者の熱意の表れであり、選手を思うがゆえの言動なのでしょう。しかし、そのアプローチは、選手の主体性や思考力を奪い、グラウンド全体の空気を息苦しいものにしてしまう危険性をはらんでいます。
指導者の「正解」をただ実行するだけの選手、ミスを恐れてチャレンジしない選手、自分の意見を言えずに黙り込んでしまう選手。そうした光景を目の当たりにするたび、私は「技術だけでは勝てない」という言葉の意味を痛感します。チームを本当に強くするのは、監督の指示通りに動く駒ではなく、自らの頭で考え、仲間と対話し、主体的にプレーできる選手たちです。そして、そうした選手を育む土壌こそが、現代の指導者に求められる最も重要な役割なのです。
続きは第2部で。

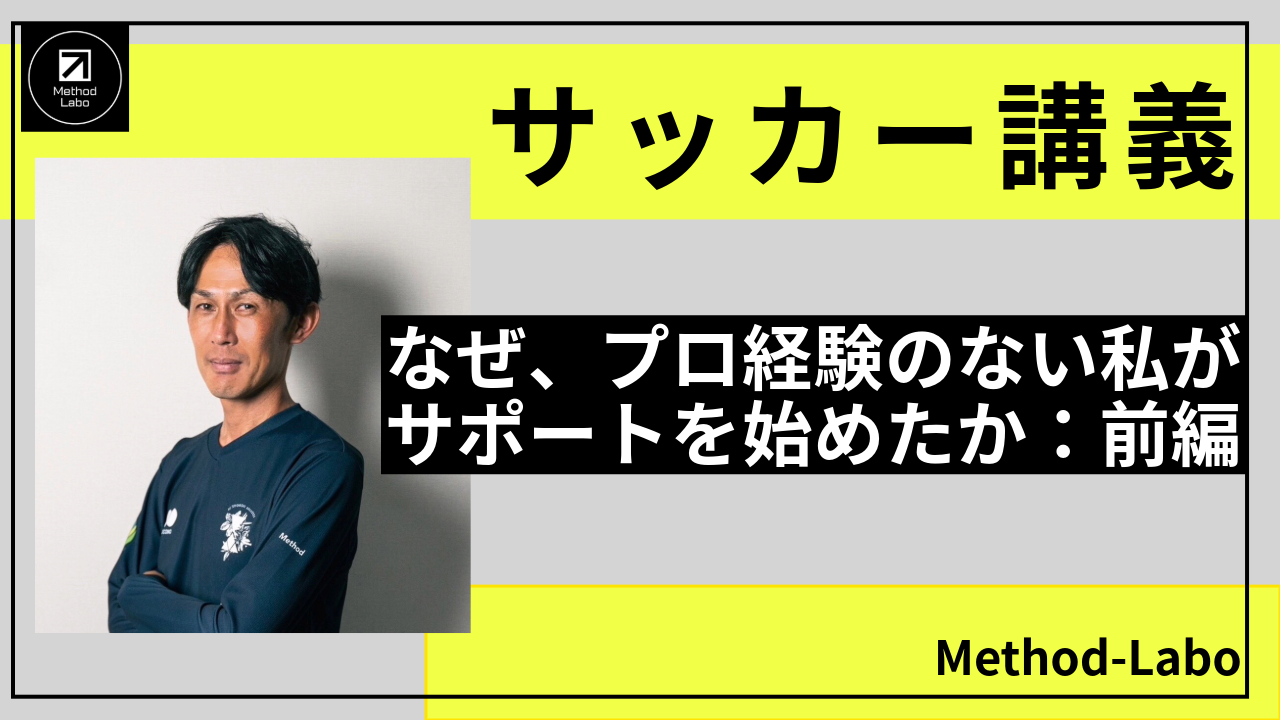
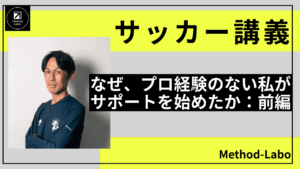
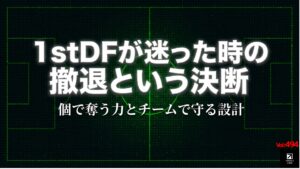


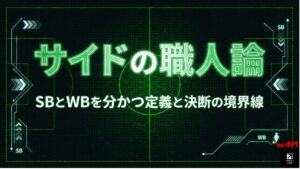

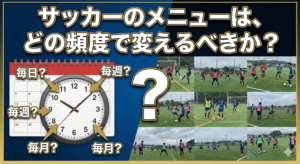
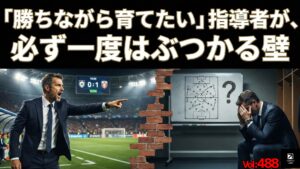

コメント