サッカーの守備において、「ズレ」はしばしばネガティブに捉えられます。多くの指導現場や試合解説では、ズレは「連携ミス」「ポジショニングエラー」といった言葉と結びつけられ、ミスとして認識されがちです。
しかし、現代サッカーの守備は静的な形を保つだけでは成立しません。むしろ、ズレは相手の動きに応じた戦術的な調整であり、「崩れ」ではなく「整える」ための動きと言えます。本記事では、このズレをどう捉え、どう活かすのかを深掘りします。
ズレは本当に“ミス”なのか?
守備における固定観念
守備は「形を保つこと」が美徳とされる文化が根強くあります。特に育成年代では、ズレが起きると即座に「怒られる」経験を積む選手も少なくありません。これにより、ズレ=悪という思考が生まれます。
ズレは動的な調整
実際の守備は静的な構造ではなく、常に動き(揺らぎ)の中で機能します。ズレは相手の動きやボールの位置に応じた調整であり、戦術的反応そのものです。
例として、前線がプレスを開始した瞬間に後方が縦方向にズレて時間を稼ぐ動きが挙げられます。
これより先を読むには【有料会員登録】を済ませてください。
*このページ区間はすべての会員様に常に表示されます*


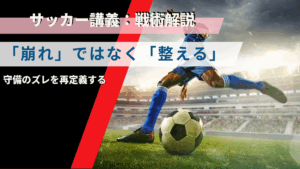








コメント