はじめに
サッカーにおいて、ゴールを奪うことは最も重要でありながら、最も難しい要素の一つです。多くのチームではエースストライカーやゴールゲッターと呼ばれる選手がチームの得点源となり、時には試合の流れを一変させるような一撃を放ちます。
ありがたいことに私自身、これまで多くの選手を指導する機会を得てきました。その中にはプロになった選手もいますし、A代表に選出された選手もいます。そういった「ストライカー」「ゴールゲッター」呼ばれる選手たちを観察していると、彼らの思考やプレー選択にはある共通点が見えてくるのです。
今回は、彼らが持ち合わせている「6つの要」について詳しく解説していきたいと思います。サッカーの得点力を高めたい方、ストライカーとして活躍したい方にはもちろん、指導者の方にも参考になる部分が多いはずです。ぜひ最後まで読んでみてください。
チームの目的からの逆算
まずは「チームの目的からの逆算」についてです。チームにおける最終的な目的は「ゴールを奪うこと」。当たり前のように聞こえるかもしれませんが、ストライカーと呼ばれる選手達(*今後は【彼ら】と表します)は、このゴールという最終目標を強く意識し、そこから逆算したプレー選択を常に行っています。
たとえば、相手を崩すためには、どういう動きが必要なのか。味方のサイド攻撃からクロスが上がる場合、どのエリアに詰めていけば最もゴールの可能性が高いのか。チームがゴールに迫るためにボールを前進させるのか、あえて動かずにスペースを作るのか。彼らはこうした判断を素早く・的確に行うことで、チームの攻撃を最大限に活かして得点を重ねるのです。
「時にはエゴイストに見えるプレーをしている」と評される場合がありますが、実際のところはチームの利益となるゴールを獲得するための最短ルートを探し続けた結果だとも言えます。この「逆算思考」は、個人の動きとチーム戦術が融合してこそ真価を発揮するのです。
個々の目的からの逆算
次に重要なのが「個々の目的からの逆算」です。彼らは、「最終的に自分がシュートを打ち、得点を決める」という強烈な意志を持っています。もちろん、仲間との連携が大前提とはいえ、最後にシュートを放ち、ネットを揺らすのは自分自身――そのための逆算が常に頭にあるのです。
例えば、ボールを受ける前のオフザボールの動き。ここで相手をうまく剥がすことができれば、よりゴールに近い位置でフリーになれます。そして高確率で決定機へとつなげられる。常に「どうすれば自分がゴールに最短で迫れるか・シュートを打てるか」を考える姿勢は、彼らに共通する大きな特徴と言えるでしょう。
【絶対領域】の理解
「自分が最も得点を奪えるエリア、得意とする形をしっかり理解している」というのも、大きな要素です。よく「デルピエロゾーン」という言葉が使われるように、選手によって得点を量産できる“絶対領域”が存在します。ゴールを狙ううえで最も可能性が高い角度、シュートスピード、あるいはボールの置き位置など、細かな感覚をしっかり把握しているのです。
たとえばペナルティ付近からミドルシュートを打つのが得意なのか、ニアサイドに飛び込んでワンタッチで流し込む形が得意なのか。選手によって異なる“ゴールパターン”を熟知し、そこに持ち込むために逆算するのが彼らの強みです。この“絶対領域”は先天的なセンスもあるかもしれませんが、トレーニングを積むことで確実に磨くことができます。
結果(成功体験)を積み重ねる
もう一つの武器は、「成功体験の積み重ね」による自信です。サッカーにおいて、ゴールを決めるとチームはもちろん盛り上がりますし、自分自身のモチベーションやコンディションも一気に高まります。そうした成功体験が繰り返されることで、さらにゴールへのイメージが鮮明になり、次の得点を呼び込む好循環が生まれるのです。
特に若い年代では、どのようにして自分のプレーを活かしてきたか、成功を掴んだかという経験が大きく影響します。たとえ一度や二度失敗しても、過去の成功体験がベースにあれば「次こそは決められる」と前向きにトライし続ける力が湧いてくるのです。
習慣化された動き・思考
彼らに共通するのが「ゴール前での習慣化された動き」です。たとえばミランで活躍したフィリッポ・インザーギ選手は、常に最後のこぼれ球を狙っているイメージがありました。シュートの後に弾かれたセカンドボールを逃さずに押し込む――こうした意識を常に持ち続けることで、“いつの間にかそこにいる”というポジショニングが習慣化されていたのです。
「どんな形でもゴールを奪う」という思考を持ち続けることで、自分の身体が自然と反応するようになります。日頃のトレーニングや試合での経験によって、この習慣はより強固になります。ですから、指導者が「常にゴールを意識しよう」と口を酸っぱく言うのは、まさにこの習慣づくりのためでもあるのです。
揺るぎない信念
最後に挙げたいのが精神的な部分、つまり「必ずゴールを奪える」という揺るぎない信念です。彼らを観察していると、失敗してもすぐに切り替えて「また次にチャンスがくるはずだ」「狙い続けていれば、最終的にサッカーの神様は自分に微笑んでくれる」といった強い気持ちを保っています。
これは決して根拠のない楽観主義ではありません。過去の成功体験、徹底したトレーニング、そして試合で培った自分の「絶対領域」への自信があるからこそ、「続けていれば必ず結果が出る」と信じられるのです。ここが欠けていると、どんなに技術が高くても得点の嗅覚を生かしきれない場面が生まれてしまいます。彼らにとって、このメンタル面の強さは得点力と同じくらい重要といえるでしょう。
本当にエゴイストなのか?
しばしば彼らは「エゴイスト」と批判されることがあります。確かに、上記のように「自分がシュートを打ち、得点を奪う」という強い意志はエゴに近い部分もあるかもしれません。しかし最終的にはチームのゴール数を増やし、勝利へ貢献することこそが本質。そこが「ただの我がまま」との大きな違いです。
一例として、かつてイタリア代表でも活躍したマリオ・バロテッリは天性の得点力を持ちながら、チームのために動けない(あるいは動かない)場面が多いと指摘されました。それが原因で評価を下げ、結果として才能をフルに活かせずに短命に終わった部分もあります。一方で、真のストライカー・ゴールゲッターと呼ばれる選手は、チームの目的に沿った形でエゴを発揮するため、チームメイトからの信頼も獲得しやすいのです。
まとめ
ここまで紹介してきたように、得点を量産する選手たちには以下の6つの要素が共通して存在します。
- チームの目的からの逆算
- 個々の目的からの逆算
- 絶対領域の理解
- 結果(成功体験)の蓄積
- 習慣化された思考と動き
- 揺るぎない信念
先天的な才能が大きいと思われがちな得点力ですが、リストに挙げたような要素を見ていくと、トレーニングや意識改革によって後天的に得られる部分も決して少なくありません。絶対領域に立ち位置を取り続ける習慣、シュートパターンの分析・練習、メンタルトレーニングによる自信の構築など、日々の地道な積み重ねがゴールを奪う力を格段に引き上げてくれます。
もしあなたがこれからストライカーとしてゴールを量産したいのであれば、まずは「ゴールから逆算する思考」を身につけてみてください。そのうえで自分に合った“絶対領域”を探り、そこにどう持ち込むかを考える。日々の練習を習慣化し、一度決めた信念はぶれずに追い続ける。こうした過程を経ることで、あなたもストライカーの素質を磨くことが可能です。
サッカーはチームスポーツでありながら、個々の能力が勝敗を左右する場面も多々あります。特に「ゴールを奪う」という部分では、ストライカーの個性が強く表れるでしょう。「あいつなら点を取ってくれる」というチームメイトの信頼感があればあるほど、より多くのパスが集まり、得点チャンスも増えていきます。ぜひこの6つの要素を意識しながら、日々のトレーニングに励んでみてください。皆さんの何かの参考になれば幸いです。
本記事が、少しでも多くの人にとって得点力向上のヒントになれば幸いです。みなさんもゴールゲッターを目指し、試合での活躍を通してサッカーをさらに楽しんでください!

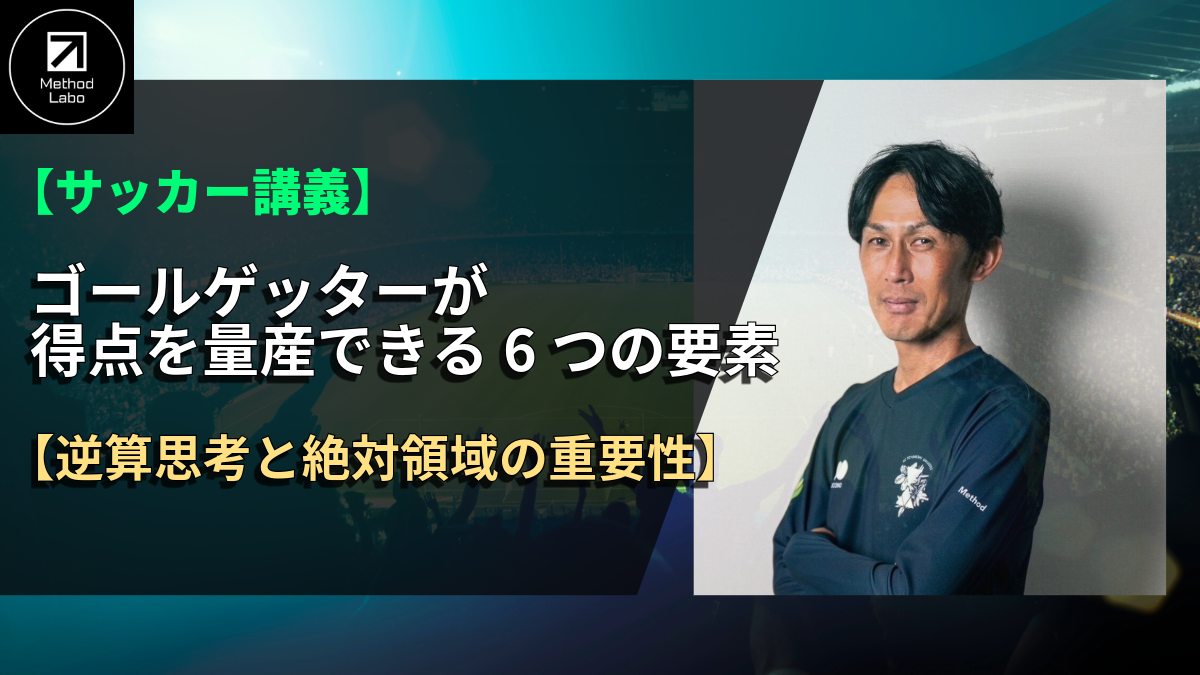
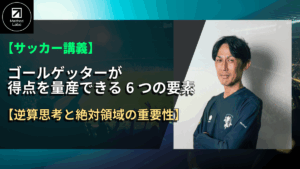








コメント