はじめに
サッカーにおける3バックは、近年ますます注目されるシステムのひとつです。欧州や南米のトップクラブの試合を観ると、4バックと3バックを状況に応じて使い分けるチームが増え、国内のJリーグでも3バックを巧みに運用する監督が増えてきています。
特にビルドアップの局面では3バックの形が一種の「武器」となり、相手の前線の守備を+1でいなして前進するメリットが数多く語られるようになりました。一方で、やはりリスクやデメリットも存在し、対策を練ってこないチームが3バックを導入すると、かえって相手のプレスの“餌食”となってしまう可能性もあります。
本記事では、3バック時のビルドアップが具体的にどのような優位性をもたらすのか、またどんなリスクやデメリットをはらんでいるのかを整理していきます。
3バックビルドアップの「優位性・メリット」
相手が2トップの場合に+1で前進できる
3バックの一番わかりやすいメリットは、相手が2トップでプレスをかけてきた場合に数的優位を作りやすい点にあります。たとえば相手が「4-4-2」や「4-2-2-2」といった2トップの配置であれば、3枚のセンターバック+GKで「4対2」を作れるため、後方で余裕を持ってボールを回せるケースが増えるでしょう。
この“+1”があることで縦パスの準備やサイドへの振り分けが比較的スムーズに行え、ビルドアップが最終ラインで破綻しにくいという利点があります
ISBが高い位置を取り、ボランチやアンカーが降りることで4バックへ可変できる
近年のサッカーでは、試合中にシステムを動的に変化させる「可変」が注目を集めています。3バックでも、サイドのCB(メソッドラボではISB「インサイドバック」と呼びますので以後ご理解を…)が高い位置をとり、ボランチ・アンカーが一列下がることで、一時的に4バックを敷く形に移行することが可能です。
たとえばビルドアップの最初の段階だけは3枚で回し、相手のプレスラインを引き出した後、ISBが一列上がって逆にボランチが降りると、4枚フラットに近い形が一瞬で作り出せます。すると相手は「3バック対策」から「4バック対策」に切り替えなくてはならず、そこにズレが生ずればチャンスを生むのです。
3バックのスライド+ウイングバックの下がりで4バックを形成
上記の可変に似た形ですが、3枚のCBが横にずれる(スライドする)一方で、逆サイドのウイングバックが最終ラインまで下がり込むことで、守備時に4枚を並べられるというメリットもあります。これは攻撃から守備への切り替え時に効力を発揮し、カウンターを受ける場面で「いきなり数的不利に陥る」リスクを軽減できます。
また、この形を使いこなせるチームは守備ブロックを4バック寄りにしておきながら、攻撃時には3バックに立ち返るなど、柔軟にシステムをスイッチできるようになります。
可変しやすい
前述のとおり、3バックはもともとボランチやサイドの選手が上下動・降りる動きを絡めることで、4バックや5バック、さらには複数の中盤構成にも移行しやすいのが特徴です。3バックの場合、ウイングバックが1列下がれば簡単に5枚になるし、サイドのCBを押し出せば4枚になるなど、選手のポジション修正が行いやすいため、相手や試合の流れに合わせた対応が可能になります。
2CBより3CBの方が互いの距離感が近い
3人のセンターバックが横並びになるイメージを思い浮かべると、2CBより自然とパスコースの距離が短くなると考えられます。特に横幅を広く使いすぎなければ、3人がコンパクトに連携できるため、ショートパスのミスが減り、ビルドアップ時の安定感が増すでしょう。
相手プレスに追われるときも、近距離でのパス交換を行いながら、タイミングを見計らって縦に入れることが容易になります。
相手プレスの人数によっては優位性を作りやすい
相手が3トップで前線からハイプレスを仕掛けてくる場合は後述するリスクが伴いますが、逆に2トップや1トップあるいは前線の守備意識が弱いチームであれば、3バックは後方で簡単に数的優位を得やすいです。さらにボランチやウィングバックと連動すれば、相手のプレスを誘い出しながら裏を突くといった意図的な崩しを仕掛けることができます。
3バックビルドアップの「リスク・デメリット」
一方で、3バックには気をつけるべきリスクも少なくありません。対策を怠ると、せっかくのメリットを活かしきれないどころか、失点や攻撃の停滞を招きやすくなります。
中央のCBがGKからボールを受けるときに角度をつけないと受けにくい
3バックの場合、GKがビルドアップの起点として中央のCBにパスを出すシーンが増えます。しかし、中央のCBがまっすぐ正面を向いて立っているだけでは、相手のプレッシャーを避ける角度が作れません。角度をつけずに受けると、簡単にプレスをはめられ、ロストするリスクが高まります。
対策としては、中央のCBが身体の向きや立ち位置を意識し、パスコースを確保する動きを習慣づけることが必要です。
3トップでプレスをかけられたときに個で剥がす能力が求められる
相手が3トップ(4-3-3など)を採用していたり、ウイングを高い位置に配置してガンガン前からくるチームと対戦する場合、3バックの数的優位は簡単に消えます。むしろ同数もしくは局面によっては数的不利に陥る可能性もあります。
そうなると、両ISBや中央のCBが1対1で相手を剥がしたり、ボールキープしながらプレスをいなし、味方へ繋ぐ個人技が必要になってきます。ビルドアップに長けた能力を持つCBがいなければ、相手のハイプレスに押し込まれやすいのです。
ロングボールの正確性が必要
3トップのプレスを掻い潜る一つの手段としてロングボールを蹴ることがあります。特に最終ライン周辺でプレッシャーを受け続けると、どうしても安全策として前線にロングキックを放るシーンが多くなるでしょう。
しかし、これが常に精度を欠いてしまうと、単なる“蹴り合い”に終始して前進のきっかけを失いかねません。3バックでビルドアップを行う以上、いざとなったらロングボールで裏を取れるだけのキック力や正確性を持ったCBかGKが求められるのです。
前線で「ズレ」を作っておかないとプレスの餌食
ビルドアップで相手の3トップをいなしながら前進する際、前線の選手たちが状況に合わせて「ズレ」を作っておくことが欠かせません。例えばFWやトップ下が絶妙な動き出しをして相手CBを引き出す、ボランチが一瞬空いたスペースに降りてくるなど、前線も連動していないと、後方が一生懸命ボールを回してもプレスを無効化できません。
連携不足のまま3バックでビルドアップを試みると、結局後方で苦し紛れのパスミスを犯す可能性が高いです。
2トップで2度追いされたときに逃げ道がないと危険
先述のように相手が2トップの場合は+1で回しやすいとはいえ、2度追いや連続したプレスに遭うと厄介です。特に中央のCBが狙われやすく、一度パスを回した後もすぐに前のFWがプレスをかけてきて逃げ場を塞ぐという守備が上手いチームだと、数的優位の恩恵を感じる前に奪われてしまうケースがあります。
したがって、後方だけで完結させるのではなく、ボランチやサイドの選手も積極的に戻って受けたり、逆サイドへ素早く振るなど、「逃げ方」を準備しておく必要があるでしょう。
3バックが横に広がりすぎるとカウンター時に広大なスペースを与える
3バックのビルドアップはサイドのCBが広く位置をとることが多いため、ロストした瞬間のカウンターに注意が必要です。横幅を極端に広く取ると、その分だけ中央が手薄になりやすく、相手のカウンターアタックが鋭いチームには格好の餌食になります。
逆サイドのウイングバックも同時に高い位置を取っていると、失った瞬間に「真ん中」「逆サイド」という両方で大きな穴が生まれる可能性も。チームとしてのリスク管理を徹底しないと痛い目に遭います。
4バックへの変化ができないとプレスにハマりやすい
3バックが万能というわけではありません。相手の戦術や修正によって「3バックのビルドアップを徹底的に狙って潰す」という作戦を取られた場合、すぐに4バックなど別の形へ変化できる選択肢がないと詰んでしまうのです。
この可変力を持っていないチームだと、「3バックしかやれない」→「相手が3バック対策を講じたら突破口がない」という単調なサッカーに陥りやすく、結果的に失点やビルドアップ崩壊へとつながるケースがよく見られます。
押さえておきたいポイント
「角度」「距離」「可変」を意識させる
3バックを活かすためには、選手一人ひとりに受け方(角度)とつなぎ方(距離)を常に意識させることが大切です。特に中央のCBとGKの間には角度が必要、ISB同士やボランチとの距離感がコンパクトすぎても遠すぎてもダメ、といった基本原則を徹底しましょう。さらに可変というオプションをチーム全体で共通認識として持っておけば、相手の出方に合わせて柔軟に形を変えられます。
個のビルドアップ力を養う
3バックの真骨頂ともいえる「相手プレスをいなす」ためには、最終ラインの選手の足元の技術や1対1のキープ力が必要不可欠です。現代サッカーではセンターバックにもドリブル突破や正確なロングフィードを要求されるケースが増えてきましたが、それは3バックを運用する上でより顕著になります。
リスク管理をチーム全体で行う
3バックはビルドアップのメリットが大きい一方、広がりすぎやカウンター対応の遅れなど、リスクに対しても常に備えておくことが必要です。センターバックだけでなく、ボランチやウイングバックの戻り、逆サイドのカバー、中央が空いたときのマーク受け渡しなど、チーム全体が同じコンセプトを共有しておくことが求められます。
4バックへの変化を用意しておく
3バックがハマらなかったときに備えて4バックや5バックへの変形パターンを練習しておくのも重要です。対戦相手やスコア状況によっては、試合途中にシステムを切り替えられる柔軟性が勝敗を分けます。たとえ3バックを基本にしていても、「4枚でしばらく守備の時間帯を作ろう」とか「5バック気味にしてカウンターを待とう」といったオプションを選手が迷いなく実行できるように準備しておくと心強いでしょう。
おわりに
3バックでのビルドアップは、相手が2トップであれば数的優位を活かせるなど多くのメリットをもたらす一方、3トップのハイプレスを受けると個の技術やロングキック精度が不可欠になるなど、リスクも明確に存在します。結局のところ、どんなシステムにも良し悪しがあり、指導者がどれだけチームに合った使い方を落とし込めるかが最大のポイントです。
特に現代サッカーでは「可変」や「柔軟性」が勝敗を左右する要素となっており、3バックを標準装備にしつつも試合の中で4バックや5バックへ移行できるチームほど、結果を残しています。
以上が「3バック時のビルドアップの優位性とリスク」についての考察でした。皆さんのチーム作りの一助となれば幸いです。

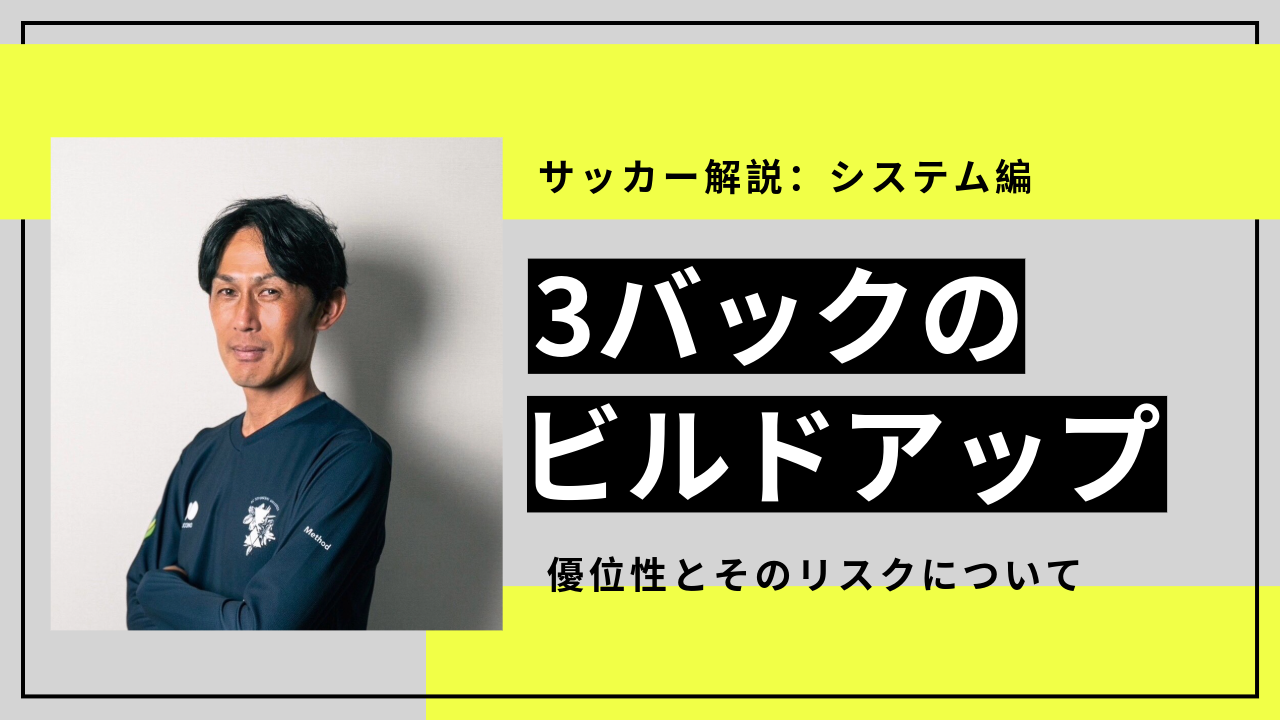
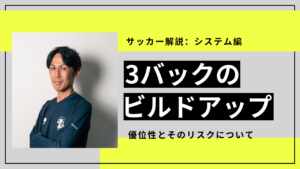
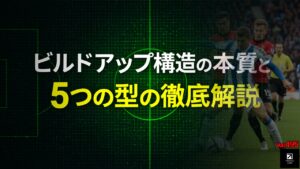







コメント