本題に入る前に、前回の記事を必ずお読みください。
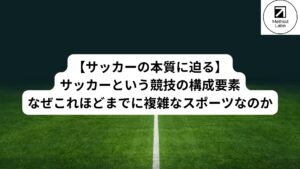
参考書書籍はこちら。
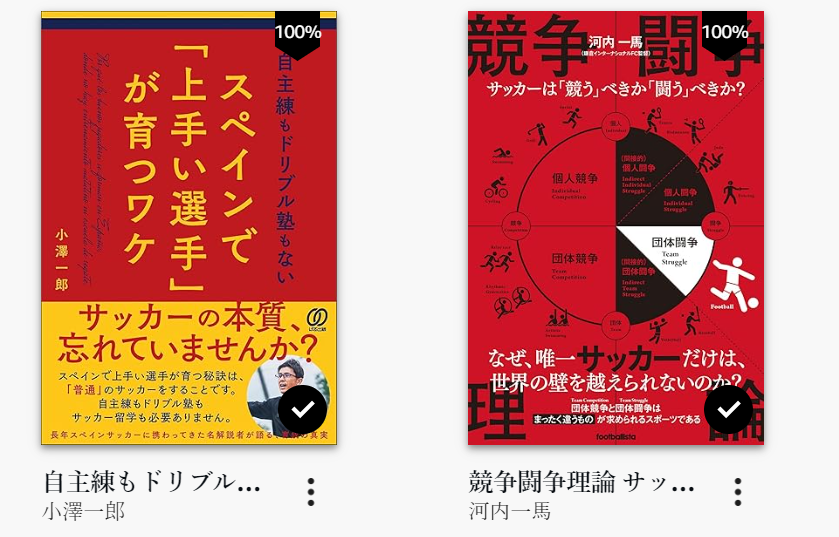
負の要因が3つ存在する
結論から言えば【団体闘争】に分類されるサッカーは、日本のスポーツ文化の背景から推測するとあまり適していません。
何度も言いますが「現時点では」です。
その理由としては以下の3点が考えられます。
・時間:サッカーが文化として馴染んでいない
・性格的要因1:内的思考・静的な集中
・性格的要因2:従順さが仇(あだ)になっている
時間:サッカーが文化として馴染んでいない
南米やヨーロッパの国々がなぜサッカーに強いのかを考えると、サッカーが彼らの文化の1部となっているからです。例えば、ブラジルやアルゼンチンでは、サッカーが生活の一部として根付いており、【闘争】が当たり前のものとされています。
その一種がストリートサッカーであると考えています。
いつでも・どこでも・誰とでもサッカーに触れる機会がある。まさに文化です。
対する日本はまだまだサッカーの歴史が浅い。
そしてむしろ窮屈になりつつあります。
最近では
□公園でサッカーをしないでください
□スパイクを履かないでください
等のお知らせや、我々が小学生・中学生だったことは小学校や中学校がいつでも解放されており自由にグラウンドを使用できたのに今では南京錠などで門が施錠されています。
サッカーできる環境はどんどん限られており、サッカーというスポーツに触れる機会が奪われつつあると考えています。
性格的要因1:内向的思考・静的な集中
前回の記事でサッカーの構成要素について触れさせていただきました。
その中の1つ。
常に自分以外の存在にも注意を払う必要がある
(外的な要因で己の行動(プレー)が変化する可能性があるので自分だけでなく他者にも集中する)
集中することは非常に重要であるが、サッカーの集中している状態というのは私たちがイメージしている集中とは異なります。(詳しくは書籍をご確認ください。)
内向的思考・性的な集中ではなく、外部のあらゆる変化に対応するような集中です。
日本人がイメージする「集中」とは静的なもので内側に向けられるイメージだと思っています。文化的な背景としては茶道や武道の際の「集中」が内向的で静的なものだと考えているからです。
それらが現代でも脈々と引き継がれている日本はまさに【内向きの集中】にはめっぽう強いが、【外向きの集中】(外部のあらゆる要因に気を配ること)にはそこまで強くないと想定しています。
よって、内向的な性格・静の集中を持つ我々にとって【団体闘争】に不向きである可能性があります。
前回の記事の冒頭で説明した【闘争】に分類される競技においては、結果が残しにくいという現状が見て取れます。しかしながら過去の成績から考えても柔道・剣道、野球(ラケット、バットスポーツ)に関して好成績を残しています。
例えば柔道。柔道においては冒頭で説明した「同時間同空間」の中で相手と戦いますが、相手= 1となっており外的要因をサッカーよりも受けにくい状況であると考えています。
次に野球です。野球は日本人との相性がものすごく良く、スポーツの文化的な背景から見ても早期に日本に導入されたものだと思っています。
攻撃と守備の役割がとても明確でありかつサインを用いてプレーすることがサッカーよりも頻繁に見受けられます。そして何よりもポジションごとの役割が比較的明確です。
例えば守備側にまわった際の守備範囲はサッカーと比較しても明確です。フォワードがDFラインまで戻って守備をすることがサッカーではありますが、野球に置いてキャッチーやピッチャーが外野のセンターエリア付近まで行って守備をすることなどはほぼあり得ませんよね?(歴史上でそんなプレーがもしあったのであれば、我々の調べ不足です)
野球は競技において間接的闘争に分類され、バットグローブなどを介してスポーツをするものです。もちろん接触プレーが全くないというわけではありませんが、サッカーと同等またはそれ以上に接触があるかと言われたら「そうではない」という結論になるのではないかと思っています。
このように、闘争競技で結果を残しているスポーツとサッカーを比較するとあまりにもサッカーは外的な要因(数学的にいうのであれば変数n)が多いのかが分かります。
*対して、その他のスポーツに関してサッカーと比較すると外的要因を受けにくいスポーツであり、同時間同空間でない条件で自己に集中すればするほど結果が残しやすいものだ理解できます。
・性格的要因2:従順さが仇(あだ)になっている
最後もスポーツ、部活動の文化的な背景が問題になっています。
それ体罰や、現代で言う「罰走」のようなものです。
書籍によると、サッカー強豪国スペインでは意味の分からない練習を指示すると小学生のような年代であっても
「やりたくない」
「サッカーをやりに来ているのでサッカーを教えてくれ」
と平気で言ってくるようです
そして中田英寿が罰走に対する発言も有名ですね。そのエピソードを下記に紹介。
「負けた罰で走るなら…」中学生だった中田英寿のひとことで、指導者は変わった
日本サッカー協会のキッズプロジェクトリーダー・皆川新一さんが外部指導員として甲府北中サッカー部の監督をしていた時のことだ。練習試合の大敗にすっかり頭に血がのぼり、部員にダッシュを命じると、中学生だった元サッカー日本代表の中田英寿さんはこう言いました。「試合に負けた罰として走るのであれば、負けた原因は監督にもある。皆川さんも一緒に走ってください」。この一言で、皆川さんの指導者人生は大きく変わりました。
朝日新聞スポーツ引用
日本人の特性としての良さでもあるが、悪さでもある従順さ。
何度もお伝えしている通り、サッカーというスポーツの中でもトップレベルの複雑な要素を持ち合わせています。その中で、何の根拠も何の理由もない罰走をこなしてしまう選手。メンタルが強くなるからと言う理由でそれを命じてしまう指導者。
ここに大きな問題があると考えています。
言われたことを従順にこなすことが場面では必要かもしれません。
しかしながらことサッカーにおいては、その構成要素が含まれていないトレーニングを何も考えず行うことは無駄に等しいです
*走ることは否定してるのではなく、根拠のない不意にやってくる指導者の気分で構成されたようなフィジカルトレーニングを我々は否定しています
この失敗したから罰として苦しい練習をする
それに耐えたらメンタルが強くなる
と言った、悪しき日本のスポーツ習慣がこの21世紀でも未だにはびこっているかと思うと恐怖でなりません。
この「罰」の日本のスポーツ文化と従順さが、団体闘争において結果の残せないのだと考えています。
この章のまとめ:我々指導者はサッカーを教えなければならない
当たり前のことですが、上記に尽きると思います。
目の前の選手が「サッカーが上手くない」のは我々指導者の責任です。
ある日突然中田英寿のような選手が
「サッカーを教えてください。監督のサッカーとはなんですか?」
と聞きに来たらどうしますか?
我々がまず「サッカー」を理解し、日々のトレーニングにサッカーの要素があるかを確認しましょう。
次回は、トレーニングがサッカーの要素を含んでいるか確認する方法を中心に紹介していきたいと思います。

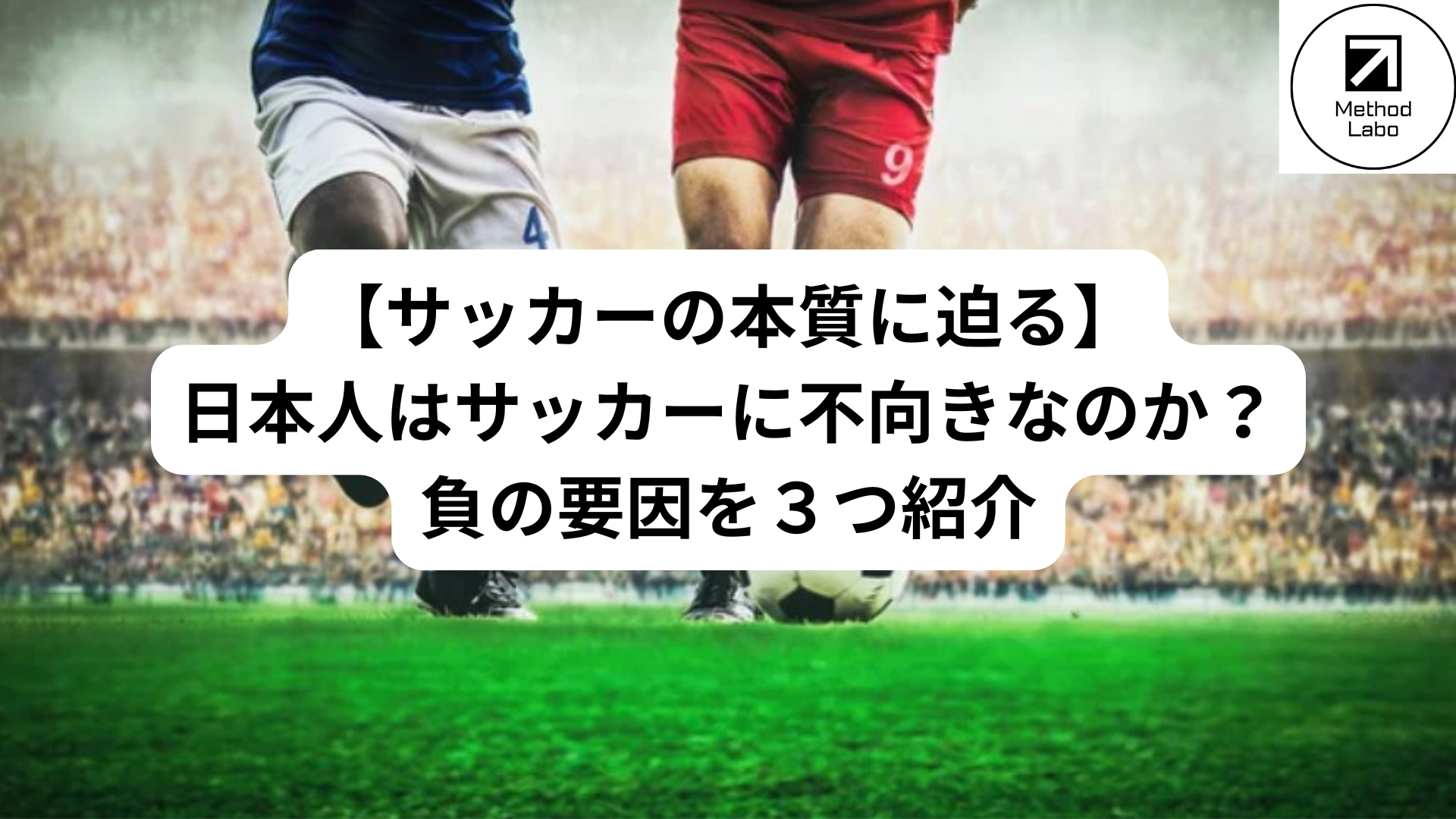
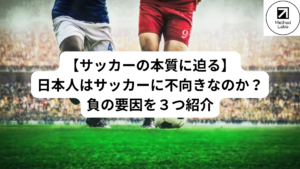
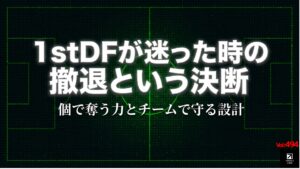


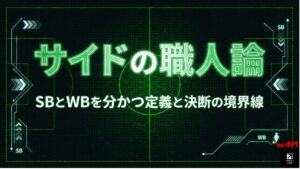

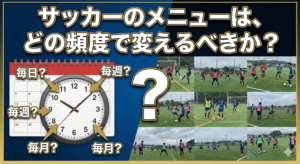
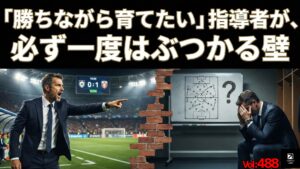

コメント