はじめに
サッカーにおいて「ピッチをどう使うか」は、戦術の根幹を左右する重大テーマです。皆さんは指導の際、「幅を取れ」「縦を急がず安全に回せ」などの声をかけることが多いかと思います。しかし、具体的に“どのエリアに選手を配置して、どんな角度と距離感を保つか”を厳密にルール化した例は、実はそう多くありません。
そんな中、名将ペップ・グアルディオラが磨き上げ、現代サッカーに大きな影響を与えたのが「5レーン理論」です。ピッチを縦方向に5つの帯域(レーン)に分割し、それぞれに役割をもたせることで、攻撃時の数的優位とパスコースの確保を常に狙う仕組みです。
今回は、この5レーン理論の基本となる発想や歴史的背景を中心にご紹介します。次回の後編では、より実戦的な応用例や具体的なチームの成功事例などを詳しく見ていきましょう。
5レーン理論とは?
ピッチを5分割し、選手配置のルールを徹底
一般的にサッカーのフォーメーションは「4-3-3」「4-2-3-1」など、数字で表されます。しかし、これらは試合前の単なる立ち位置だという方もいますし、おもにバランスよく配された布陣であったり、ディフェンス時の形を示すことが多く、いざ攻撃へ転じると前線や中盤の人数配分が大きく変化してしまいます。(可変ありき)
そこで注目されたのが位置取りをシステム化する「5レーン理論」なのです。
5レーン理論では、ピッチを左右の端(サイドレーン)、それに隣接する2つのハーフスペース(ハーフレーン)、そして中央のセンターレーンの計5帯域に分割します。配置上の最大のポイントは、「一列前にいる味方とは同じレーン上に重ならないこと」。こうすることで斜めのパスコースが常に保たれ、三角形の頂点が生まれるわけです。
なぜ5レーンに分けるのか?
サイドと中央を同時に活かすための最適解
サッカーでゴールを奪うには、中央突破とサイド攻撃を状況に応じて使い分ける必要があります。しかし、中央に寄りすぎれば相手の守備に密集エリアに捕まり、サイドに張りすぎれば中央への連係が薄れますし、限定されて追い込まれるというというジレンマが生じがちです。
そこで、“サイドレーン(左右2つ)”“ハーフスペース(左右2つ)”“センターレーン(1つ)”という5つの帯域に等分し、それぞれ1人ずつ配置する形が理想としました。すると、サイドを有効に使うウイングやオーバーラップするサイドバック、内側のハーフレーンに立つインサイドハーフや偽サイドバック、中央レーンでプレーするトップやトップ下がそれぞれ分散配置されやすい状況が基準をつくることで生まれます。
「縦に並ばない」で三角形をキープ
5レーン理論には、次のような原則が含まれます。
- 一列前の味方とは同じレーンに立たない
- 二列前の味方とはむしろ同じレーン上に位置することもある
- 隣接するレーン同士は常に斜めの距離感を保ち、サポート角度を形成
この結果、相手から見て守備対象のマークが難しくなり、攻撃側が数的優位を作りやすくなります。しかも、単に“パスコースが多い”だけではなく、ボール保持者の斜め前方に常にサポート役が現れるため、スムーズなポゼッションを維持しやすくなり、前進の可能性も高まります。
ポジショナルプレーと5レーン理論の関係
「数的・位置的優位を獲得する」ポジショナルプレー
グアルディオラの提唱するポジショナルプレーは、「選手個々の能力だけでなく、ピッチ上で常に数的優位を生み出す配置をとることで、攻守で効率よくゲームを進める」という考え方です。5レーン理論は、このポジショナルプレーを具体的に形にする“配置のテンプレ”と言ってもいいでしょう。
例えば、4-3-3でスタートしていても、攻撃時には実質「2-3-5」や「3-2-5」のように前線に5人が並ぶ形へ変化する。このとき、それぞれの5人が5レーンをきれいに埋めると、相手は横にスライドさせられ、さらに中央への意識もそがれやすくなる可能性があります。こうした優位を利用して、ハーフスペースに走り込む選手を使ったコンビネーションや、サイドからのカットインを狙う多彩な攻撃を繰り出します。
伝統的なフォーメーションとの違い
王道の4-4-2ではあらかじめ全エリアをまんべんなくカバーしようとする傾向が強く、個々の選手の裁量でそのエリアを活用する傾向があります。しかし5レーン理論は、必ず5つのレーンをすべて埋めるようにし、その中でポジションチェンジを行うといったチームとしての約束事が生まれます。単純にフォーメーションの立ち位置に立つだけでなく、ボールのある局面ごとに最適なバランスを保とうとする“空間(レーン)の管理”をする意識とその能力が重視されます。
5レーン理論のメリットと課題
メリット:幅と深さを同時に取れる
- 幅: ウイングやサイドバックがサイドレーンを確保して、相手ディフェンスラインを広げる
- 深さ: トップやシャドーがセンターレーンで最前線に張るほか、ハーフスペースに入り込む動きで相手ゴールに近づく
これにより、ピッチのあらゆる横幅と奥行きを最大限に使い、相手に的を絞らせない攻め方が可能となります。
課題:動きすぎないコントロールと選手の理解度
一方で、全員が好き勝手にポジションチェンジをすると「いつの間にかレーンが重複している」「3人以上が縦に並んでしまう」といった混乱が起こりかねません。5レーン理論を活かすには、選手それぞれのタスクの明確化、連動連携をもって最終的には5つのレーンにを管理するという考え方を浸透させるが必要です。
まとめ
ここまで、グアルディオラの「5レーン理論」を中心に、ピッチを縦に5分割するという新しい戦術発想の概要をご説明しました。
まとめると、
- ピッチをサイドレーン・ハーフスペース・センターレーンの5帯域に分ける
- それぞれのレーンに1人ずつ配置し、一列前後の選手が同じレーンに被らないようにする
- 三角形やひし形のサポートを維持し、ポジショナルプレーの数的優位を作る(ロンドの延長上)
というシンプルなルールではあるが、現代サッカーの高度な戦術を支える大きな柱となっています。
あなたのチームでも5レーンの考え方を取り入れてみれば、思わぬ攻撃パターンの発見につながるかもしれません。皆さんの参考になれば幸いです。

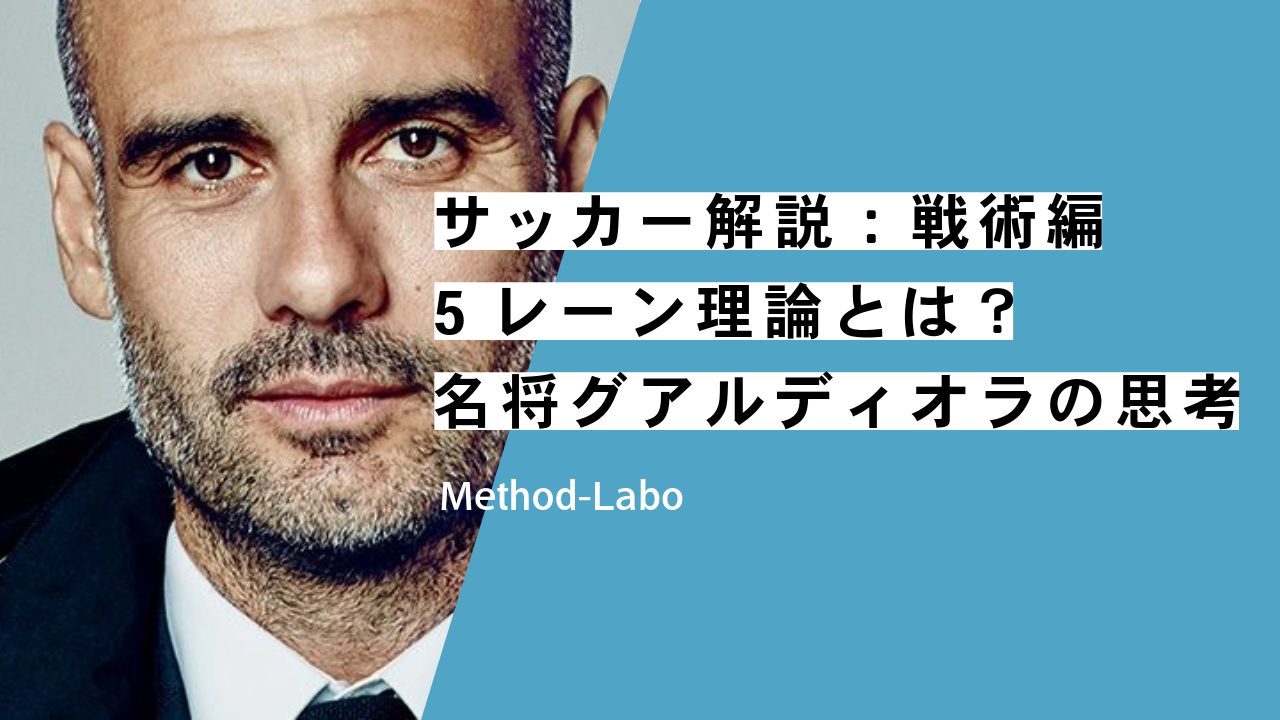
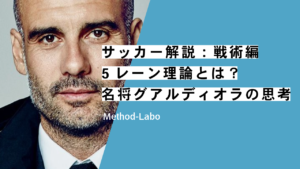








コメント