感覚に頼らず「言語化」する
我々は「言語化」の必要性がスポーツにおいては高まっていると考えています。もちろん、以前から監督やコーチが選手に対して声をかける場面は当たり前にありました。しかし、「声かけ=言語化」とは少し違います。
たとえば「もっと走れ」「ボールを回そう」といった漠然とした言葉は、確かに選手への指示ではあるものの、選手の頭の中にどんなイメージを描かせるかはまちまちです。「もっと走る」とは、どのスペースに向かって走るのか、何を目的に走るのか、味方との距離感はどう保つのか――そういった要素を細かく整理し、短い言葉にまとめて伝える行為こそが「言語化」といえます。
言語化が持つ3つの重要な要素
- 短く伝えられること
長々とした説明は、実際のトレーニングや試合のスピードに追いつきません。素早く、端的に伝えるためには短いフレーズが求められます。 - 誰もが理解できること
サッカー経験が豊富な選手から初心者の選手まで、全員が同じイメージを共有できる言葉がベストです。 - 共通のイメージを抱けること
同じ言葉を聞いたとき、選手・指導者・スタッフが“同じ方向”を向いてこそチームの統一感が生まれます。
この3つを意識するだけでも、チーム全体の指導やプレーの精度は確実に上がります。いわば言語化は、チーム内で統一された「共通言語」を作り上げるプロセスなのです。
言語化がもたらす具体的なメリット
では、この言語化はどんなメリットがあるのでしょうか。大きく分けて以下のポイントが挙げられます。
共通認識の形成
一つのプレーや戦術について「これってどういうことなんだろう?」という疑問は、選手同士のなかでも意外と起こりがちです。しかし、言語化によって“端的な言葉”が用意されれば、迷いが生じにくくなります。
理解の定着と修正指示のしやすさ
言語化された戦術やプレーの概念があると、指導者はピッチサイドから「〇〇のときは××を意識して」など、状況に即した修正を的確に行えます。これは選手にとっても大きなメリットです。試合中やトレーニング中に飛んでくる言葉が「自分のどの行動を修正すればいいのか」を明確に示してくれるからです。
逆に言語化ができていない状態だと、指導者が「もっとしっかりやれ」「そこは違う」というような曖昧な指示しか出せず、選手も「どこがどう違うのか」を理解しづらいままプレーを続けることになります。
言葉の力
言語化の重要性を示す例として挙げられるのが、ヨハン・クライフ率いるバルセロナです。サッカークリニックで取り上げられていたので思わず読み込みました(笑)彼らが「ドリームチーム」と呼ばれて欧州カップを制し、国内リーグでも圧倒的な強さを誇った頃、すでにポジショナルプレーやパスワークの概念がある程度言語化されていたといいます。
クライフ自身は選手時代にアヤックスやオランダ代表で「トータルフットボール」という革新的なスタイルを体得していました。しかし、偉大な選手が偉大な指導者になるかといえば、必ずしもそうではありません。クライフは自身の体験や感覚を理論的に整理し、それを選手たちに伝える術を培っていきました。感覚値を伝えられるといった点が彼のすぐれた能力です。
その結果、バルセロナの選手たちは「ここではこのポジショニングを取り、次の瞬間にはどこへパスを出すか」という共通認識を当たり前のように身につけ、まるで機械のように連動したパスワークを実現させました。短い言葉であっても、その背後にある理論や意図を共有できたからこそ、あの伝説的なチームの躍進があったといわれています。
「強豪クラブだからこそできた特別な例」だと感じる方もいるかもしれませんが、この考え方をカテゴリーが違ったとしも実践してみる価値は十分にあります。むしろ言語化を導入することで、一見普通に思える日々の指導に新たな発見や刺激が生まれるでしょう。
言語化を取り入れるためのポイントと未来への展望
では、実際にあなたの現場で「言語化」を取り入れるためには、どのようなステップを踏めばいいのでしょうか。以下のポイントを押さえると、よりスムーズに取り入れられるはずです。
- チームのキーワードを整理する
まずは「味方のサポート距離」「プレスのかけ方」「ビルドアップの合図」など、チームにとって重要な概念やプレーをリストアップしましょう。そこから、最も大事にしたいものに絞って短いキーワードを設定します。 - 短いフレーズで表現する
とにかくシンプルに。短くまとめる。 - 実際の練習や試合で繰り返し使う
作った言葉を実際のトレーニングで“繰り返し”使い続けることが大事です。どれだけ良いフレーズでも、慣れていなければ意味がありません。積極的に声かけし、選手同士でも使うように促しましょう。
我々の取り組み
私たちメソッドラボとしても、この「言語化」に最もこだわってきました。「経験で見つければいい」「試合をこなせば慣れる」といったスタンスを取るケースが未だにあります。しかし、理想的なプレーを引き出すためには、曖昧な感覚に頼るだけでなく、はっきりとした言葉で整理し、共有することが重要です。様々な練習メニューや戦術コンセプトを短い言葉に落とし込んで「基準」をつくり、同じ共通言語で話せる環境づくりをすることはとても重要です。
【まとめ】
「言語化」は、単に“声をかける”という行為とは大きく異なります。重要なのは、短く、誰もが理解でき、そして共通のイメージを抱ける言葉をつくり出し、それをチームに浸透させること。そして、そのものの再現性を高めるための手段です。
- 選手同士のイメージを一致
- 自分のプレーを客観的に振り返り、成功要因や失敗要因をはっきり言葉で捉えられる
- 指導者間でもノウハウを共有し、より高いレベルを追求で
これらはすべて、技術と戦術のチームの底上げにつながります。
言語化を意識して指導することで、選手たちの動きはより統一され、プレーの再現性が高まります。さらに「自分はなぜこのプレーを選択したのか?」といった振り返りも言葉を通じて行いやすくなり、選手の理解度も高まることでしょう。
ぜひ、あなたのチームでも「言語化」を試してみてください。最初は慣れないかもしれませんが、一歩踏み出せば「こんなにスムーズに伝わるのか」「これほどまでに選手が理解してくれるのか」と驚くはずですチームの大切にしたいポイントを“短く、わかりやすく、イメージしやすい言葉”で表してみましょう。指導の質が一段と向上するはずです。
私たちメソッドラボも、これからのサッカー界をさらに面白くするために、言語化に拘っていきたいと思います。皆さんの参考になれば幸いです。

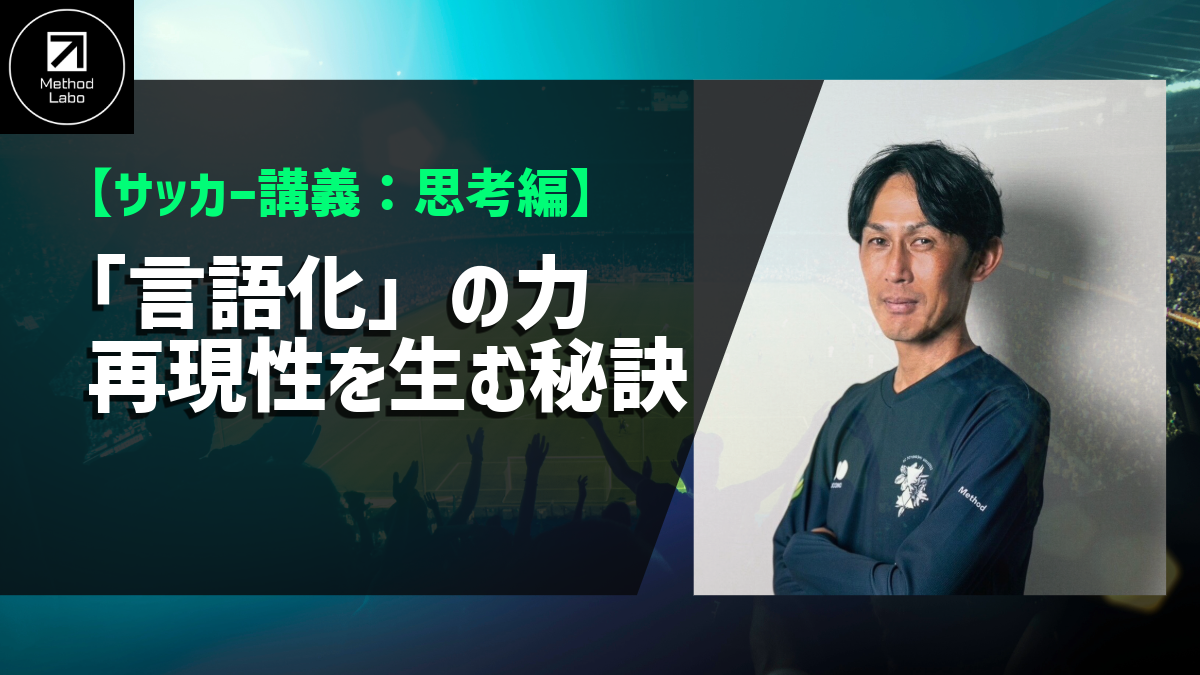
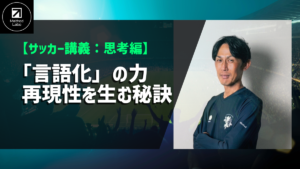








コメント