はじめに
日本サッカー協会(JFA)は、指導者のレベル向上とサッカー界全体の発展を目指してライセンス制度を整備しています。たとえば「C級からB級へ」「B級からA級へ」というように、階段を一つずつ上がることで、より深い戦術理解や指導技術を得ることができる仕組みです。しかし、「実際にはどうすれば次の段階へ進めるのか」「ライセンス取得の試験や講習で求められることは何か」については公式サイトだけでは情報が限られており、経験者に直接聞くことが多いのが現状ではないでしょうか。
私自身も指導者としてスタートした頃は、先輩コーチやライセンスを先に取得した仲間に相談しながら、自分の指導法をブラッシュアップしてきました。そこで本記事では、私が「一つ上のライセンスを目指そう」と考える方々に伝えたい、必要な知識や理解すべきこと、そして今すぐ取り組める具体的な行動についてまとめていきたいと思います。あくまでも私個人の経験に基づく考え方ですが、何かしら参考になる点があれば幸いです。
ライセンス取得の意義を再確認する
ライセンスのステップアップを目指すにあたり、まず「なぜ自分はその資格を取得したいのか」を明確にしておく必要があります。周囲が持っているから、自分のキャリアに有利だからといった理由ももちろんあるでしょう。しかし、それだけではモチベーションの維持が難しくなることがあります。ライセンスを持つことで自分がどんな指導者になりたいのか、どう選手を成長させたいのかといった“指導哲学”をしっかり持つことが重要です。
日本サッカー協会のライセンス制度は、指導者同士の共通言語を得る場であり、学びを深める機会でもあります。C級からB級へ、あるいはB級からA級へと進む中で、「より専門性の高い視点で選手を導けるようになる」等といった利点があります。こういった意味やメリットを、まずは今一度心に刻んでみてください。
トレーニングを人に見てもらう
私が常々意識しているのは、自分のトレーニングを他の人に見てもらうことです。これはいわゆる“公開トレーニング”の形をとっても構いませんし、個人的に信頼できる指導者仲間を呼んでフィードバックを受けるだけでも十分価値があります。自分の指導内容を客観的に捉えることは、想像以上に難しいものです。自分が良かれと思ってやっている指導が、実は選手の混乱を招いているケースもありますし、その逆もあり得ます。
もちろん、なかには「人に見られるのは少し抵抗がある」と感じる方もいらっしゃるでしょう。特に指導歴が浅いと、自分の指導メニューやコーリングを批判されるのではないかと不安になることも少なくありません。しかし、そうした不安を取り除くには、まず行動してみるのが一番です。観ている人たちは“ジャッジを下す審査員”ではなく、“一緒に成長を考えてくれる仲間”というスタンスでいてくれる人を選ぶといいでしょう。私自身も、様々な指導者の方に自分のセッションを見学してもらい、感じたことを率直に言ってもらう機会を大切にしています。
そのうえでディスカッションができれば、新たな発想や改善策が自然と生まれます。
私は指導者が10人いれば10通りの考えや視点があると思います。常に成長をしたいと思っているので、新しい視点や自分とは異なる視点をどんどん知りたいと思っています。よって明確な1つの答えはありません。積極的にディスカッションして考えを深めましょう。
人のトレーニングを見学する
同時に、他の指導者のトレーニングを見学する機会を積極的につくることも欠かせません。私自身は、プロの現場や育成年代の現場に足を運び、様々な監督・コーチの視点やトレーニング手法を学ぶよう心がけてきました。たとえば、ロアッソ熊本の大木監督やジュビロ磐田U-18の安間監督、名古屋グランパスU-18の三木監督、カマタマーレ讃岐の濱崎ヘッドコーチなど、幾多の指導者の下を訪ねては、練習風景だけでなく考え方や指導の意図を直接伺う機会を得てきたのです。
矢野隼人さんなどは印象に残っており、自分の成長を支えてもらったと非常に感謝しています。柏レイソルのリカルドロドリゲス監督もその一人です。そのほかにもあげ出したらキリがないくらいの方のトレーニングを見せていただきました。
“学び方”には個人差があるため、一概に「この人のところへ行けば間違いない」というものではありません。それでも、異なるクラブや異なる指導者を見ることで、今まで気づかなかった視点を得られる可能性は高まります。ときには「自分のチームには合わないな」と思うような手法に出会うかもしれませんが、それもまた学びの一つです。自分とは違うやり方を知ることで、自分のスタイルがより明確になることもあります。
テーマ別の指導案を作成する
ライセンス講習や実技試験、現場での実践を通じて必要とされるのは、目的に合わせたトレーニング設計の力です。試合をイメージしながら、何を獲得させたいかを明確にし、そこから逆算してメニューを組み立てる。その一連のプロセスを自分の中で形にするために、テーマ別の指導案を作成する習慣をつけるのがおすすめです。
たとえば、「ビルドアップ時の立ち位置の改善する」「サイド攻撃」「守備のチャレンジとカバー」といった具体的なテーマを設定し、それぞれの段階(ウォーミングアップ、各パート、ゲーム形式など)においてどんなタスクを与えるか、どのように声をかけるか、どれだけの時間や人数設定で行うかなどを紙に落とし込んでみましょう。頭の中でイメージするだけでも大切ですが、書き出すことでより整理されることが多いです。
また、作成した指導案を実際に試してみて、「選手の反応はどうだったか」「狙いどおりに進まなかった部分はどこか」といったフィードバックを取りながら改善を重ねることが重要です。単に“トレーニングをやりました”で終わるのではなく、“なぜそれが良いのか・どう機能しているのか”を説明できる指導者が、次のライセンスレベルに繋がります。
まとめ:継続的な学びこそが次のステージにつながる
ライセンスが上がれば上がるほど、求められる視点や対応力、選手とのコミュニケーションはより高いものを求められます。しかし同時に、指導者としてのやりがいや選手を成長させる喜びは、一段と大きなものへと変わっていくでしょう。私自身もいまだに勉強中の身であり、“完璧”を目指すのではなく、日々のトレーニングや試合を通じて少しでも前進しようと取り組んでいます。
以上が、「一つ上のライセンスを目指すにあたって必要な知識、理解するべきこと、今やるべきこと」について、私自身の経験を交えながらまとめた内容です。あくまで参考程度にしてください。
ライセンス制度は指導者を支える大きな枠組みですが、その中身をいかに生かすかは、最終的に各指導者の姿勢と行動にかかっています。今回の記事が少しでも参考になれば幸いです。

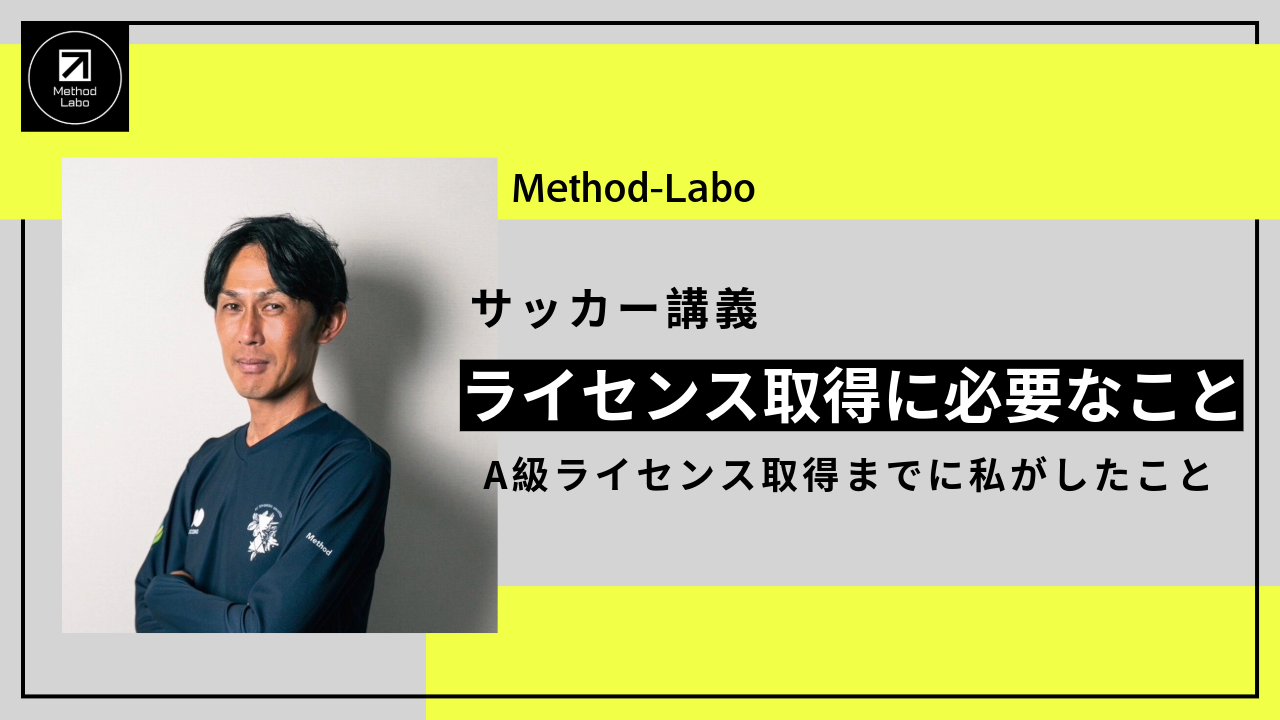
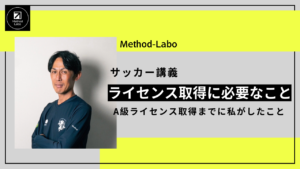








コメント