はじめに
サッカーの試合が長い…
と思ったことはありません?我々でももちろんあります(笑)
Jリーグの試合を初めて観戦した方の中には、「なんだか90分が長く感じる」「得点シーン以外が退屈…」と率直に感じる方も多いのではないでしょうか。確かにサッカーという競技は他のスポーツと比べて得点が少なく、ゴールが決まる瞬間だけを待ってしまうと、どうしても間の時間が長く退屈に感じられてしまうことがあります。
しかし、実はサッカーの試合展開の中には、目に見えにくい数多くの駆け引きがあります。特に「戦術」に着目すると、チームごとに異なる攻守のスタイルや戦い方が見えてきますし、さらに「選手個々の動き」を追うことで、個々がどのような役割を果たし、チームの勝利に貢献しているのかを理解できるようになります。
この記事では、サッカー観戦が退屈に感じてしまう理由をざっくり整理し、その上で「戦術」と「選手の動き」という二つの視点で試合を楽しむポイントを詳しく紹介します。まずは、どうしてサッカー初心者が90分を“つまらない”と感じやすいのかを見ていきましょう。
「90分がつまらない」と感じる理由
得点シーンが少ない
サッカーでは他競技と比べてゴール数が少ない試合も珍しくありません。例えば野球・バスケットボール等なら1試合に何度か得点シーンが訪れるのが当たり前ですが、サッカーでは試合終盤まで0-0という場合もあります。そのため、「得点こそが盛り上がるタイミングだ!」と考えてしまうと、待ち時間が長すぎて退屈に感じるかもしれません。ですが、ゴールが決まったときの爆発的な歓喜は、滅多に起こらないからこそ大きいとも言えます。
攻防の意図が分かりづらい
試合を通してボールをキープしている時間帯やパスを回している場面は多いですが、「なんで横や後ろへパスするんだろう?」と疑問に思うことはありませんか? 特に初心者にとっては、前に攻めないプレーは消極的に見え、「早くシュートまで行ってほしいのに」ともどかしく感じるはずです。しかし、実はそれらのパスには明確な目的があり、相手の守備を崩すために“泳がせる”戦術が隠されていることも多々あります。
特殊なルールが分かりにくい
サッカー特有のオフサイドやVAR(ビデオアシスタントレフェリー)の判定など、馴染みのないルールがあると混乱しやすいものです。せっかくゴールが決まって盛り上がったのに、「オフサイドで取り消し!」となると、ルールを知らない人にとってはストレスが溜まる場面かもしれません。オフサイドを正確に理解するには時間がかかりますが、ざっくりでも分かれば「今のプレーはオフサイドかも!」など、試合展開を先読みして楽しめるようになります。
ボールを持っていない選手の動きに気づきにくい
サッカーはピッチ上で常に22人の選手が動いていますが、テレビ中継や初心者の目線では、ついボールホルダー(ボールを持っている選手)だけに意識が行きがちです。ところが、実はボールを持っていない選手たちが「どう動くか」によって攻撃と守備のシナリオが作られています。この“オフ・ザ・ボール”の動きに気づかないと、試合展開の面白さを半分しか味わえていないとも言えるでしょう。
戦術面で注目すべきポイント
サッカーは単なる個人技だけでなく、チーム全体の戦い方(戦術)が勝敗に大きく影響します。ここでは、特に大きな見どころとなる戦術の要素を三つ紹介します。
システムの違い(スタートポジション)
まず試合前に確認しておきたいのが「システム(陣形)」です。例えば、「4-4-2」「4-3-3」「3-4-3」など、DF-MF-FWの人数の並びで表記されます。これは監督の方針やチームの特徴を表すもので、4バックで安定を図ることが多かったり、攻撃を重視するチームは前線に厚みを持たせた布陣を選ぶことが多かったりします。
試合前のスターティングメンバー発表ではシステム図が表示されるので、「お互い4-4-2同士」「片方は3バック、もう一方は4バック」といった違いを意識してみましょう。相手チームのシステムや選手構成によっても、自チームの陣形が微妙に変化することがあります。そうした駆け引きを見つけると、「なるほど、監督はこういう狙いでこの布陣を採用したんだな」と理解が深まり、単なるポジションの数合わせ以上の意味を感じられるようになります。
ブロック形成とプレスのかけ方
サッカーは「攻撃」だけでなく「守備」がとても重要。守備のスタイルもチームごとに大きく異なります。主なモノとして以下のようなものがあります。
自陣にブロックを作って守る
相手にボールを持たせておき、自陣に全員がしっかり構え、コンパクトにスペースを消すやり方です。見た目には消極的に感じるかもしれませんが、格上相手にも失点を最小限に抑えられる理にかなった戦術です。Jリーグでも、堅守速攻型のチームはブロックを固めて少ない失点で勝ち切るスタイルを貫くことがあります。
前線からプレスをかける
相手に楽にパス回し(ボールポゼッション)をさせないよう、前線のFWや中盤のMFが積極的に相手DFやGKまで追い回すスタイルです。この「プレス」がハマれば、高い位置でボールを奪ってそのままゴールへ直行できますが、前がかりに行くぶん後ろが手薄になり、かわされた瞬間に一気にピンチに陥るリスクもあります。プレスを仕掛けるのが好きなチームは、最初からガンガン前に出ていき、華やかな攻防シーンが多くなるので観ていて迫力があります。試合中は「どの位置まで守備陣形を上げているのか」「前線の選手がどこからプレスに行くのか」に注目してみてくださいチームが試合状況に応じて戦い方を変える様子を観察するだけでもかなり面白いです。
ビルドアップ(攻撃の組み立て)
守備以上に見どころが多いのが「ビルドアップ」と呼ばれる攻撃の組み立て方です。大きく分けると以下の二つに分類されることが多いでしょう。
ポゼッションサッカー
ボール支配率を高めながら細かいパスを繋いで相手を崩すスタイルです。最終ラインの選手も大きく蹴らずに短いパスでビルドアップし、中盤の選手と連携しながら相手守備を動かしていきます。川崎フロンターレなどパスワークに定評のあるチームだと、このスタイルで多くのチャンスを作り出すことがあります。相手を揺さぶり、じわじわとギャップを作って最後にスパッと崩す瞬間は最高に見応えがあります。
カウンターサッカー
奪ったボールを素早く前線に送り、相手の守備が整う前にゴールを狙うスタイルです。ロングパスやドリブル突破に長けた選手がいるチームだとこの形がはまりやすく、一瞬の隙を突いてビッグチャンスを得られます。守備陣がブロックを作って耐え、ボールを奪った瞬間に前線の快速FWへ送る――という流れが決まると一気にスタジアムが沸き立つでしょう。
試合中に「後ろでボールを回しているチーム」と「奪ったら即ロングカウンターするチーム」が対決すると、自然と「ポゼッションvsカウンター」の構図が生まれます。どちらのスタイルに軍配が上がるかは選手の特徴やチーム力の差にもよるので、見ているだけでワクワクしますね。
選手の動きに注目するポイント
戦術や戦い方を大まかに把握したら、次は選手個々の動きに注目してみましょう。特に初心者が見落としがちな「ボールを持っていない選手の動き」はサッカー観戦を何倍も楽しくしてくれる重要な要素です。
ボールを持っていない選手の動き(オフザボール)
実はサッカーのプレーの大半は、ボールを持っていない選手によって成り立っています。攻撃時にボールを持っていない選手が相手DFを引きつけたり、逆サイドに流れたりすることでフリーのスペースが生まれ、ゴールチャンスに繋がっているのです。例えば、ボールを持っている選手の周囲にいる味方が常に動いてパスコースを作ってあげる姿を見つけると、彼らの連携の深さが分かります。
守備時も同様に、ボールを持っていない選手が相手FWの動きを先読みしたり、マークを絞ったりして攻撃を未然に防いでいます。中盤の選手が相手パサーを潰しにいく動きがあれば、後ろのDFはそのタイミングでラインを上げる、というように連動した動きがあるのです。こうしたオフザボールの動きを追うと、一見地味に見える時間帯でも様々な駆け引きが行われていることに気づきます。
プレスの連動とカバーリング
もう一歩踏み込んで“選手単位”で見るなら、どのように連動してプレスをかけているかがポイントになります。通常、一人が頑張って追いかけ回しても意味がなく、全員が連携してパスコースを消しながら追い込んでいくのがプレスの基本です。
例えばFWの一人が相手CBへ猛然と走り出したタイミングで、中盤の選手が相手ボランチにパスさせないようマークを詰め、さらにサイドバックも外の選手をケアする――このように連動して相手を追い込んでいくのです。もし一人でもサボっていたら、その選手のマークを通じて簡単にパス回しされてしまうかもしれません。試合中「チームの守備意識が高いな」と感じるのは、こうした連動にブレがない時です。逆に、連携が取れていないと相手に前を向かれ、守備が後手に回りやすくなります。
カバーの動きにも注目してみましょう。プレスをかけている選手がドリブルで抜かれたとき、すぐ後ろの選手がスライドしてマークにつけるかどうかが大きな差になります。これが上手く機能しているチームは、大崩れしにくい堅い守備を見せる傾向があるでしょう。
サイドチェンジへの対応
攻撃側は相手のブロックを崩すため、わざとサイドにボールを集めて逆サイドに大きく展開することがあります。サイドチェンジが成功すると、守備側が反対側へ素早くスライドできない一瞬の間にスペースが生まれ、効果的なクロスやカットインに繋がる場面が多いです。
逆に、守備側が素早く対応できれば「今、サイドを変えたのにもう戻ってきている!」と攻撃側が攻め手を失うこともしばしば。中盤の選手が素早く横にスライドしてコースを切るのか、あるいはサイドバックが自分のマークをきっちり受け渡すのかなど、連携力の高さが問われます。華麗なサイドチェンジで一気に相手を崩せたらスタジアムは大歓声。一方、それを完璧に対応して凌いだ時の守備の集中力もまた見どころです。
まとめ
サッカー初心者がJリーグの試合を観て「つまらない」「90分が長い」と感じるのは自然なことです。得点が少なかったり、ボールを持っていない選手の動きが見えにくかったり、難しいルールがあったり――戸惑う要素は多いでしょう。しかし、戦術や選手の動きに少し目を向けるだけで、見慣れなかった間の時間に数えきれない駆け引きやチームの努力が隠されていることに気づきます。
今回紹介したポイントに注目していると、たとえスコアレスの試合でも「なるほど、こうやって崩しを狙っているんだ」「今の守備連携が完璧だった!」と興奮できる場面がきっと増えるはずです。一つ一つのプレーや配置に注目していると、気づけばあっという間に90分が過ぎているかもしれません。
初めから全てを理解する必要はありません。まずはお気に入りのチームや選手を見つけて応援しながら、「今日はここに注目してみる」くらいの軽い気持ちで観戦してみてください。観れば観るほど、サッカーの奥深さが見えてきます。チームカラーの違いや個性豊かな監督同士の頭脳戦、そしてピッチ上で繰り広げられる選手たちの駆け引きなど、サッカーには数えきれないほどの魅力が詰まっているのです。ぜひ「戦術」と「選手の動き」に注目してみてください。きっと新しい発見があると思います。
みなさんの何かの参考になれば幸いです。

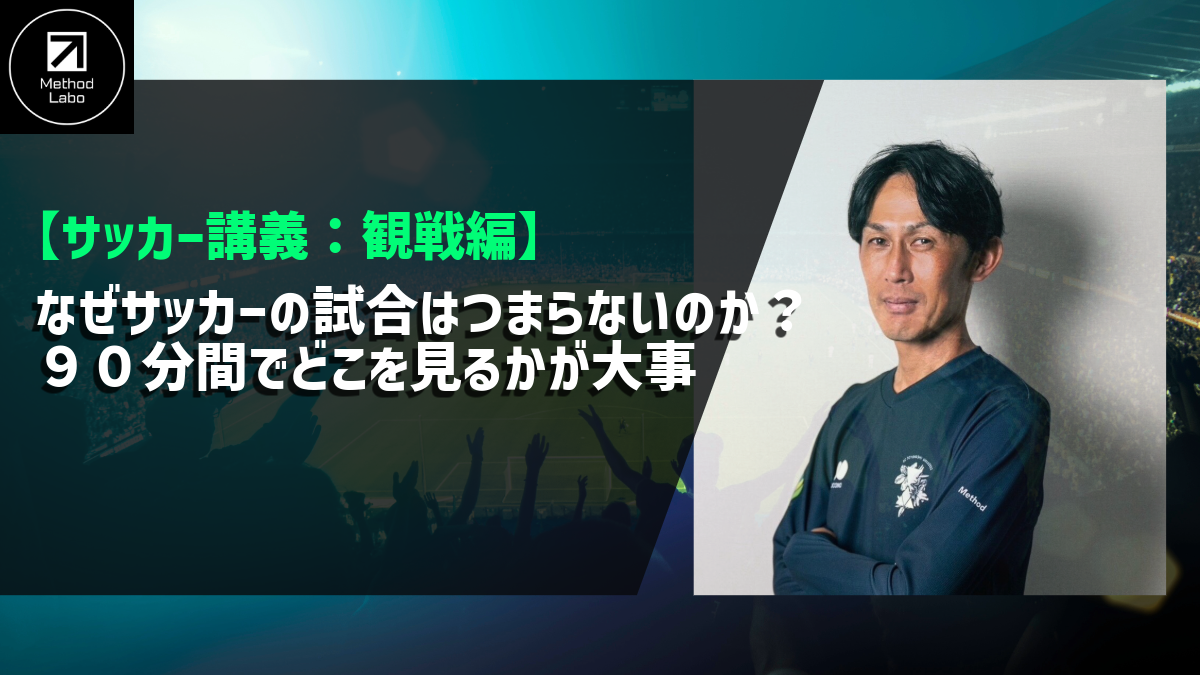
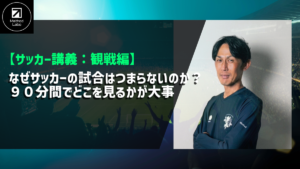








コメント