はじめに
今回は守備特集です。
・チームとしてどんな戦術をとるべきか決まっていない
・実際メリット・デメリットが良く分かっていない
・良いトレーニング方法を知りたい
上記の内、1つでも当てはまった方は是非ともご覧ください。
サッカーにおいて「守備」は、チームの安定感を左右する重要な要素です。
特に、プロの舞台では守備の整備が未成熟なチームは一瞬で崩されることも珍しくありません。そんな中、大まかに「ゾーンディフェンス(ゾーン守備)」と「マンツーマンディフェンス(マンマーク守備)」という2つの大きな戦術が存在します。
- ゾーンディフェンス: ピッチをいくつかのエリアに区切り、各選手が担当エリアを守る発想
- マンツーマンディフェンス: 各選手が相手プレーヤー1人に密着マークし、1対1で対抗する発想
どちらの戦術にも一長一短があり、現代サッカーでは状況に応じて使い分けられる場合も多いです。本記事ではそれぞれのメリット・デメリットを見ていきたいと思います。
ゾーンディフェンスの定義と仕組み
ゾーンとは?
ゾーンディフェンスとは、「人ではなくエリアを基準に守る」戦術です。特定のエリア(ゾーン)を守ることで連携して相手の攻撃を防ぐ戦術です。そのメリットの一つは、スペースを守ることができることです。各選手が担当するエリアを明確に決め、相手の進攻をスペースごとにブロックすることで、相手の攻撃を効果的に封じ込めることが可能です。
ピッチをいくつかのゾーン(エリア)に分割し、選手は自分の担当エリア内に入ってきた相手に対してアプローチします。最大の狙いは、スペースを効果的に埋めることでゴールへ至る攻撃ルートを塞ぐことです。
たとえば、4-4-2の2列ブロックで整然と守る欧州のチームや、南米クラブが導入する堅固な中盤ブロックなどが典型例です。マンマークと違って「相手がどこに動いても追いかける」必要はなく、基本的には自分のエリア内で待ち構える形をとります。
仕組みの特徴
- スペース管理: ボールサイドに人数を寄せながら、逆サイドも最低限カバーするなど、全体のバランスを重視
- 味方との連動: 1人抜かれても他の選手がカバーできる距離感を保つ
- コンパクトな陣形: ライン全体を前後左右にスライドさせ、相手の攻撃を封じ込める
ヨーロッパのトップクラブやJリーグの多くのチームでは、ゾーン守備をベースにしながら「ここはマンマーク気味に行く」などのハイブリッドスタイルを採用している場合も多いです。
マンツーマンディフェンスの定義と仕組み
マンマーク守備とは?
マンツーマンディフェンスは、サッカーにおいて古くからあるスタイルで、「人が人に付く」戦術です。
守備側の選手がそれぞれ相手選手1人を担当し、相手がどこへ動こうと、ピッチのどこへ行こうと追いかけてマークする。守備範囲を相手によって決定するため、「誰を見るかが明確」**となり、指示や責任分担がシンプルです。
仕組みの特徴
- 1対1で勝つ意識: 自分が負けない限り、相手に自由を与えない
- 相手のエースを封じやすい: 特定の危険な選手に専属マーカーを付ければ攻撃を寸断可能
- 運動量が増える: 相手が左右に動けば同じ距離を走らされるため、守備側の負担が大きくなる
マンツーマンは昔のカテナチオにも取り入れられ、現代でもアタランタ(イタリア・セリエA)などがフィールド全域でマンマークを仕掛ける攻撃的守備を実践しています。
守備の安定性・スペース管理――両戦術の違い
ゾーンの強み:守備ブロックが崩れにくい
ゾーンディフェンスは、主に“スペースを埋める”発想であるため、陣形が崩れにくい特徴があります。
- プレーヤー同士の距離感が保ちやすい
- 「相手が走り回っても無闇に追いかけない」ので、ゴール前に大きなスペースを空けにくい
- 結果的に守備ブロックをコンパクトに維持しやすく、失点リスクを減らせる
たとえば、アトレティコ・マドリード(シメオネ監督)の4-4-2ブロックは、ゾーンを意識した堅守の典型例です。相手がボールを動かすたびにスライドし、ブロックの形を整えてゴール前に隙間を作らせない守備は、まさに“チーム全体でスペースを管理”している見本と言えるでしょう。
マンツーマンの弱み:陣形がばらつく可能性
これより先を読むには【有料会員登録】を済ませてください。
*このページ区間はすべての会員様に常に表示されます*

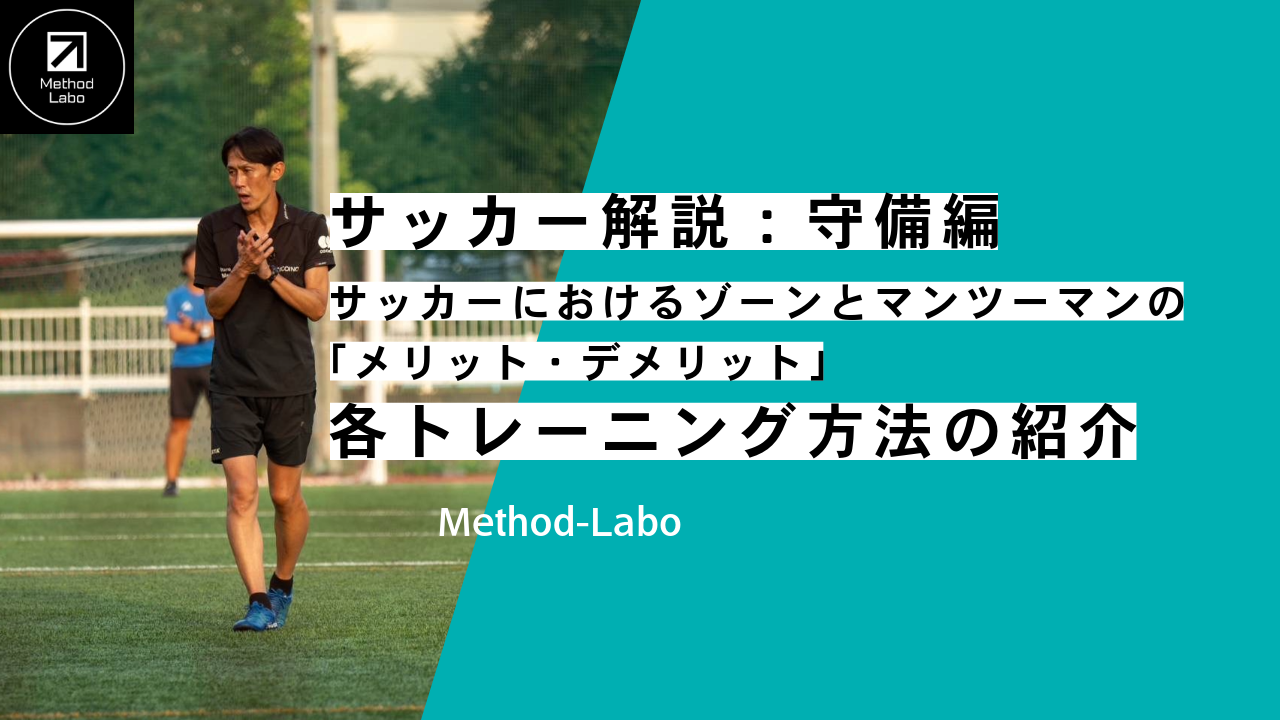

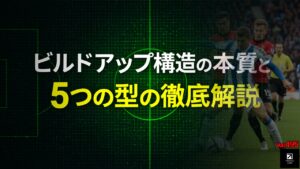







コメント