「ボックス占拠」とは、攻撃時にペナルティエリア(ボックス)内へ複数の選手を計画的に配置し、相手守備に数的優位を作る戦術です。単なる“人数をかける”ではなく、構造とタイミングを緻密に設計して機能させます。
目次
具体的な特徴と狙い
1. 中央密集型フォーメーション
- 例:4-3-1-2、3-4-2-1
- ウイングを使わず中央に人を集め、場面によっては最大5人がボックス侵入します。
2. IH(インサイドハーフ)の飛び出し
- 中盤の選手が適切なタイミングでボックスへ侵入します。
- 「セントラルウインガー」としてのIHがSB裏を狙う動きが鍵です。
3. 2トップの役割
- ポストプレーでCBを釘付けにする/背後への走りで最終ラインを押し下げる。
- これにより他の選手が動けるスペースが生まれます。
4. WB(ウイングバック)の浮きポジション活用
- 相手SBが内側に注意を向けると、外のWBがフリーになります。
- そこからの折り返しやクロスで、ボックス内の人数を生かして仕留めます。
なぜ「ボックス占拠」が有効か
- 数的・心理的プレッシャーを守備側に与えられます。
- 即時奪回がしやすく、カウンターリスクを抑えられます。
- 「2タッチ原則」などプレー精度を高める指示と併用しやすい構造です。
「2タッチの原則」とは?
「2タッチのほうが好きだ。ダイレクトはミスになる確率が高い」という考えを前提に、原則“2タッチ以内”でプレーする規律です。テンポと精度を両立させ、中央密集での細かな連係を安定させます。
どういう意味?なぜ重要?
1. 1タッチ目:コントロール
- 受けた瞬間に次のプレーを想定して止めます。
- 体の向き、スペース、相手位置を意識した準備のタッチです。
2. 2タッチ目:パス or ドリブル
- 迷わず次のアクションへ移ります。
- これにより速いテンポと高い精度を両立できます。
なぜ「ダイレクトプレー」より2タッチなのか?
- ダイレクトは華麗だが、ミスの確率が高く意図が伝わりにくい。
- 2タッチなら判断の余裕と精度を確保できます。
- 特に**中央密集(ボックス占拠)**では、細かなパス回しの正確性が命です。
まとめ
- ボックス占拠は、ボックス内への計画的な人数配置とタイミングで得点確率を高める設計です。
- 2タッチの原則は、その設計を乱さず素早く正確に回すための基準です。
- 中央密集型の4-3-1-2や3-4-2-1を土台に、IHの飛び出し/2トップの役割分担/WBの外フリーを組み合わせ、各局面で2タッチを徹底する――この一貫性が、決定機の質と回数を同時に引き上げます。

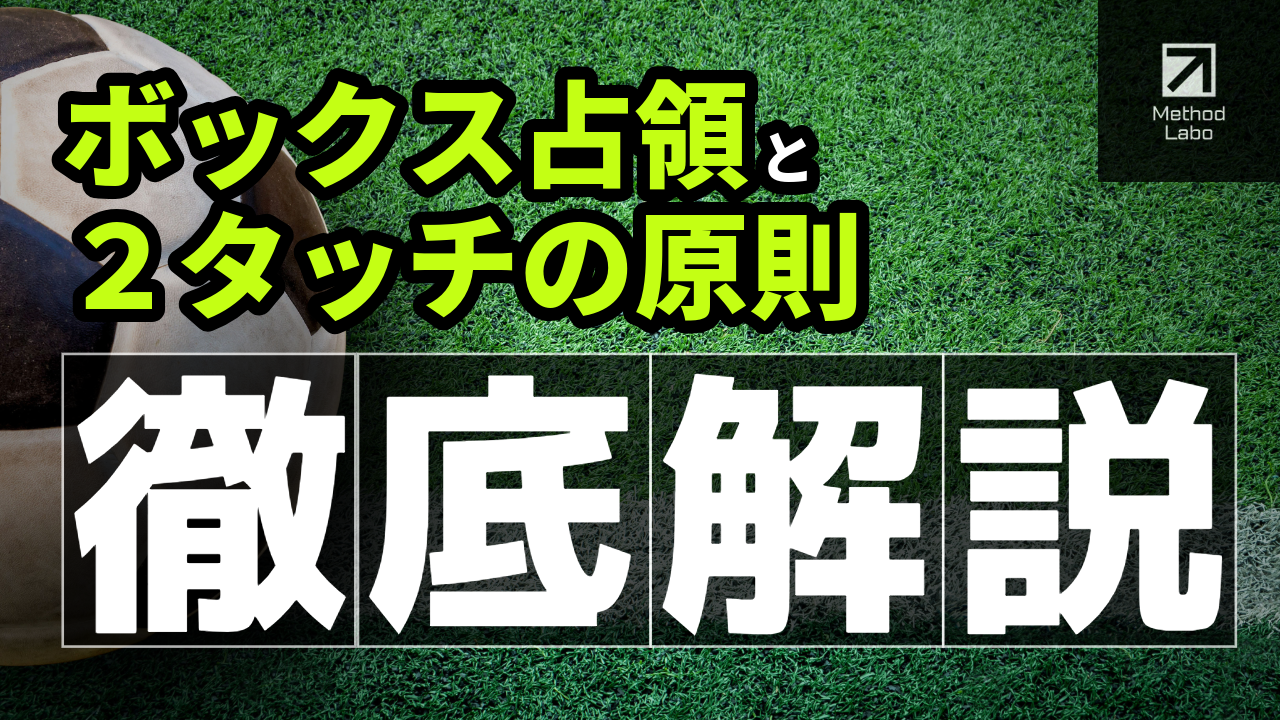
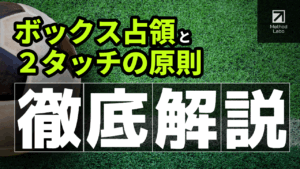








コメント