はじめに
サッカーの指導現場では「ピッチの幅を最大限に使え」という原則がよくあったと思います。選手がサイドに広がることで相手守備陣を横に引き伸ばし、間のスペースを突くという、多くのチームが採用してきた攻撃の基本です。
一方で、「最小限の幅」という言葉が注目されてきました。これは、タッチライン際のウイングを置くのではなく、意図的に中央とハーフスペースへ人員を集約し、重要エリアでの数的優位と切り替えの密度を高める方法です。
ユリアン・ナーゲルスマンを含む複数の監督が状況に応じて用いてきた考え方で、従来の幅重視とは対照的な逆の理論に位置づけられます。今回は、その背景にある考え方、ピッチ上でのメカニズム、得失点差に直結しやすい長所と、同時に課題を整理します。
基本概念
何を“最小限”にするのか
ここでいう「幅を絞る」とは、常時タッチラインに接する幅取り役を固定しないことを指します。横幅は主にサイドバック(SB)やウイングバック(WB)の状況的な前進、あるいは中央の選手の一時的な外流れで必要最低限を確保。狙いは、中央〜ハーフスペースに人員とプレー関与を集中させ、短距離のパス交換と前向きの受け直しを増やすことにあります。
これより先を読むには【有料会員登録】を済ませてください。
*このページ区間はすべての会員様に常に表示されます*

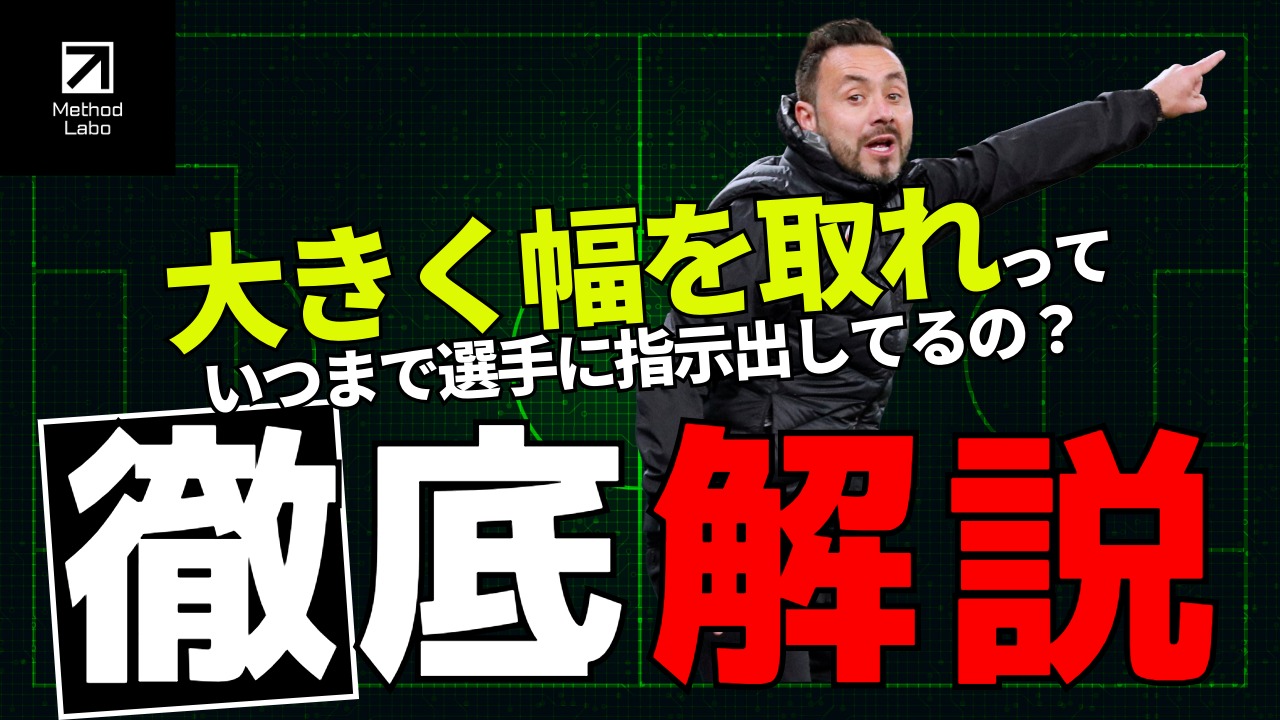
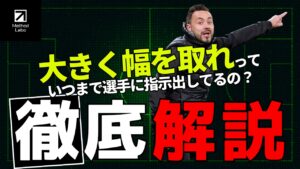








コメント