現代サッカーの戦術を観察すると、かつては4バックが主流であったディフェンスラインの構成に、明らかな変化が見られます。ヨーロッパのトップリーグからJリーグに至るまで、「3バック」システムを採用するチームが、近年顕著に増加しています。
かつては守備的な戦術、あるいは特殊なシステムと見なされることもあった3バックが、なぜ今、再び世界のサッカーシーンで脚光を浴びているのでしょうか。
今回はこの「3バック」という戦術システムを解剖します。その基本的な定義から始め、3バックが増加している背景を個別に分析。両者の目的の違いを比較することで、現代サッカーの戦術トレンドに迫っていきます。
3バックとは何か?
3バックとは、その名の通り、3人のセンターバック(CB)を基本とした守備陣形のことです 。一般的には、「3-4-3」「3-5-2」「3-4-2-1」といったフォーメーションで用いられます 。このシステムの特徴は、最終ラインの両サイドに、攻撃と守備の両方で重要な役割を担う「ウイングバック(WB)」を配置する点にあります 。これにより、局面に応じて守備にも攻撃にも厚みを持たせることが可能な、柔軟性の高い布陣です 。
欧州で3バックが増加する背景
ヨーロッパのトップレベルで3バックの採用が増加している背景には、現代サッカーの戦術トレンドに対応するための、いくつかの合理的な理由があります。
1. プレッシング回避とビルドアップの安定
近年の欧州サッカーでは、前線の選手から相手のビルドアップに対して激しいプレッシングをかける戦術が主流となっています 。多くのチームが2トップ、あるいは1トップ+トップ下という形で前線からプレッシャーをかけてくるのに対し、3バックはゴールキーパーを含めると後方で数的優位(4対2や4対3)を作りやすくなります 。これにより、プレッシャー下でも安定してボールを保持し、攻撃の第一歩であるビルドアップを成功させやすくなるのです 。トーマス・トゥヘル監督やアントニオ・コンテ監督といった指導者たちが、3バックを戦術の軸として成功を収めたことで、その有効性が広く認知されました 。
2. ウイングバックの進化
3バックシステムを機能させる上で不可欠なのが、ウイングバックの存在です。現代サッカーにおけるサイドの選手は、単なる攻撃や守備の専門家ではなく、攻守両面で高い貢献が求められる「万能型」へと進化しています 。カイル・ウォーカー選手やテオ・エルナンデス選手のように、驚異的な運動量、スピード、そして攻撃センスを兼ね備えた選手が、3バックの両翼として機能することで、チームの戦術的な幅は大きく広がります 。
3. 可変システムとしての柔軟性
現代の3バックは、固定されたシステムではありません。試合の状況に応じてその形を自在に変化させられる「可変システム」としての柔軟性が、多くの監督に好まれる理由です。例えば、攻撃時にはウイングバックが高い位置を取る「3-4-3」で攻め込み、守備時にはウイングバックが最終ラインまで下がることで「5-4-1」という堅固なブロックを形成できます 。このように、攻守のバランスを試合中に調整しやすいことは、特に実力が拮抗した強豪同士の対戦において、大きなアドバンテージとなります 。
Jリーグで3バックが増加する背景
Jリーグにおいても3バックの採用は増加傾向にありますが、その背景にある理由は、欧州とは少し異なる側面が見られます。
1. 守備の安定とカウンター重視
Jリーグでは伝統的に、まず失点をしない「守備から入る」ことを重視するチームが多く存在します 。3バックは、最終ラインの中央に3人のセンターバックを配置するため、ゴール前の最も危険なエリアの守備を厚くすることができます 。この中央の堅固な守備をベースに、ボールを奪った後、前線へ素早くロングボールを送るカウンター戦術を組み合わせるスタイルは、Jリーグにおいて非常に効果的です。サンフレッチェ広島や町田ゼルビアといったクラブは、この3バックを基盤とした戦い方で、安定した結果を残しています 。
2. 日本人選手の特性との適合性
3バック、特に運動量が求められるウイングバックというポジションは、日本人選手の特性と相性が良いという側面もあります 。日本人選手は、勤勉で運動量が豊富、かつ戦術理解度が高い選手が多いとされています 。90分間、タッチライン際を献身的にアップダウンし、監督の戦術的な要求を忠実に実行できる選手が多いため、3バックシステムを機能させやすい土壌があると言えるでしょう 。
3. 可変システムの一般化
欧州と同様に、Jリーグでも試合中にフォーメーションを変化させる「可変システム」の導入が進んでいます 。例えば、基本布陣は4-4-2でも、守備時にはサイドハーフが最終ラインに下りて5-3-2のような形になる、あるいは攻撃時には3-4-2-1から2-3-5のような超攻撃的な布陣に変化するなど、試合中の可変はもはや一般的です 。3バックは、こうした可変システムのベースとして非常に機能しやすいため、戦術的な柔軟性を求める監督たちにとって、魅力的な選択肢となっているのです 。
「考察」Jリーグと欧州における目的の違い
このように、欧州とJリーグの双方で3バックの採用は増えていますが、その主な目的には明確な違いが見られます。
- 欧州での目的: 主に、相手の激しいプレッシングを回避し、安定したビルドアップから攻撃の主導権を握ることを目的として採用されるケースが多いです 。
- Jリーグでの目的: 主に、中央の守備を固め、守備の安定性を確保し、そこから効率的なカウンター攻撃に繋げることを目的として採用されるケースが多いです 。
この目的の違いは、それぞれのリーグに所属する選手の特徴や、背景にも起因しています 。個の突破力やフィジカルが重視される欧州に対し、日本では組織的な連携や運動量が強みとなることが多いです 。
結論
3バックという戦術システムは、もはや一つの固定された形ではありません。それは、現代サッカーの複雑な要求に応えるための、極めて柔軟なものです。
欧州では、ボールを支配し、攻撃の主導権を握るための「攻めの3バック」として。Jリーグでは、守備を安定させ、勝利への現実的な道筋を描くための「守りの3バック」として。同じシステムでありながら、その目的や運用方法は、それぞれの戦術的環境に応じて、異なるものとなっています。
なぜ3バックが増えているのか。その答えは、このシステムが持つ柔軟性と、それぞれのリーグが直面する戦術的な課題に対する、合理的な解決策としての価値にあると言えるでしょう。この地域による戦術的な違いを理解することは、現代サッカーをより深く楽しむための、重要な視点となります。





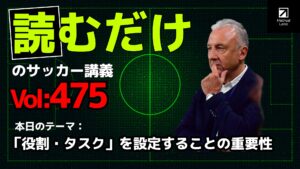
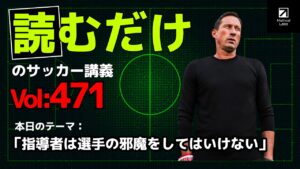

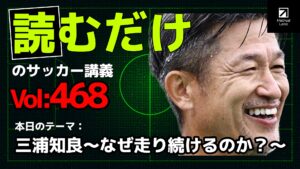


コメント